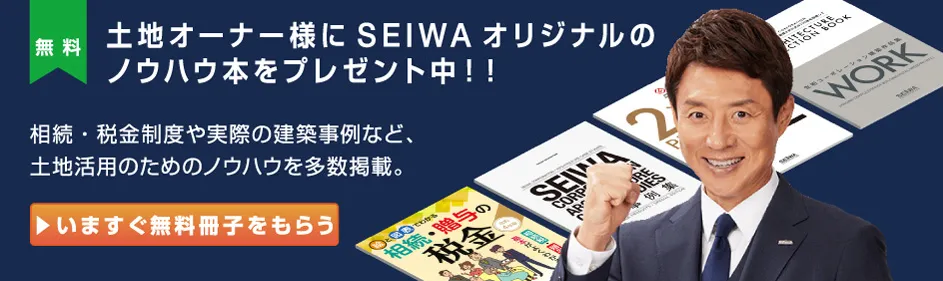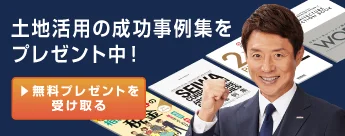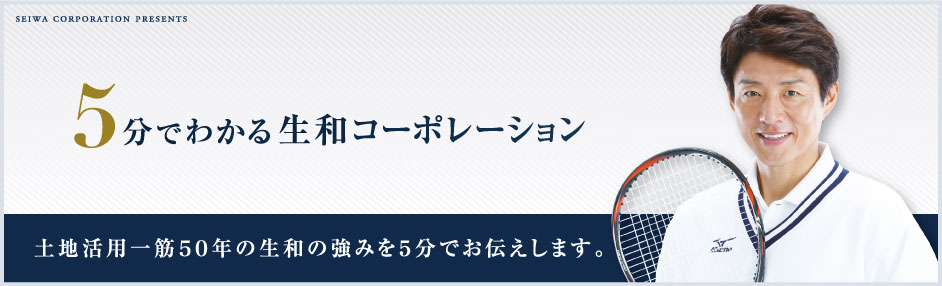マンション経営を続けていくうえで「法人化すべきかどうか」は、多くのオーナー様が判断に悩まれるのではないでしょうか。
法人化は税金面でのメリットが期待できる一方、設立時のコストや煩雑な会計処理といった負担も増加します。こうしたメリット・デメリットを把握したうえで、法人化を検討することが大切です。
この記事では、マンション経営の法人化のメリット・デメリットをわかりやすく解説します。併せて、会社形態の選び方や、設立の手続き・流れについても紹介しますので、法人化を検討する際の参考にしてください。
この記事の目次
マンション経営の法人化とは
マンション経営の法人化を検討する際は、以下の2つのポイントを理解する必要があります。
- ポイント① 個人経営と法人経営の違い
- ポイント② 法人化を検討すべき年収・物件規模の目安
マンション経営における法人化とは、個人事業主として経営していた不動産を、法人格を持つ会社として経営することです。個人経営と法人経営では、節税効果や経費の計上範囲など、さまざまな面で違いがあります。
まずは、法人化の基本的な概念と個人経営との違い、法人化を検討する目安となる年収や物件規模について解説します。
個人経営と法人経営の違い
マンション経営における個人経営とは、会社設立の手続きをせずに、個人事業主として経営を行なうことです。それに対して法人経営は、個人とは別人格である「法人」を設立し、その法人によって経営を行なう形態です。
つまりマンション経営の法人化とは、ご自身で会社を設立し、その会社がマンションを所有・経営することを指します。
個人経営と法人経営の違いは、以下のとおりです。
| 個人経営 | 法人経営 | |
|---|---|---|
| 事業開始時の手続き | 税務署に開業届を提出 | 法務局に会社設立の登記申請書を提出 |
| 事業開始にかかる費用 | なし |
|
| おもな税金 |
|
|
| 事業主(株主)の責任範囲 | 無限責任 | 有限責任 |
| 社会的信用 | 法人と比べて低い | 個人と比べて高い |
| 会計・経理 | 確定申告 | 法人申告 |
| 赤字の繰越 | 3年(青色申告の場合) | 10年 |
法人化を検討すべき年収・物件規模の目安
マンション経営の法人化を検討する目安は、「年間所得800万円以上」または「年間売上1,000万円以上」で、その理由は税制面によるものです。
個人事業主の場合、所得税は所得額に応じて税率が上がる累進課税制度が適用されます。所得が800万円を超えると税率は23%、900万円を超えると33%、1,800万円を超えると40%と税率が上がる仕組みです。
一方で、法人税は年間所得が800万円以下であれば15%、800万円を超えた場合は、超えた分に23.2%の税率が適用されます。個人の所得税に比べると税率の変化がゆるやかで、税金の負担を抑えることが可能です。
また、個人事業主の場合、年間売上が1,000万円を超えると消費税の課税事業者となります。しかし、法人化することで課税の基準となる売上がリセットされ、その後2年間は消費税の納税が免除されます(課税事業者を選択しない場合)。
ほかにも、5棟以上所有するなど、事業的規模で経営している場合も法人化を検討するタイミングといえるでしょう。
マンション経営を法人化する4つのメリット

マンション経営を法人化する4つのメリットは、以下のとおりです。
- メリット① 法人税率の優位性で収益を最大化できる
- メリット② 経費計上範囲が広がり節税効果が高まる
- メリット③ 役員報酬で所得分散が可能になる
- メリット④ 相続税対策として活用できる
上記のなかでも、特に節税効果や経費計上範囲の拡大は法人化による大きなメリットといえます。ここでは、マンション経営を法人化する4つのメリットを詳しく解説します。
法人税率の優位性で収益を最大化できる
マンション経営を法人化するメリットの一つは、所得税と法人税の税率差を利用した節税効果です。
先述のとおり、個人事業主に課される所得税は、所得額が増えるほど税率が上がる累進課税制度です。例えば、年間の課税所得が800万円の所得税率は23%ですが、4,000万円を超えると45%になります。そこに住民税10%が加わるため、税負担の合計が50%を超えるケースもあるのです。
一方、資本金1億円以下の法人に課される法人税は年間800万円以下の所得に対して15%、800万円を超える部分に対しては23.2%です。個人に比べて税率が低く、地方法人税や住民税、事業税などを含めた実効税率は35%程度となります。
なお、課税所得が「900万円超1,800万円以下」の場合、個人の実効税率は43%(所得税33%+住民税10%)となり、法人の実効税率を上回ります。
つまり、個人の年間所得が900万円を超えたあたりから、法人化による節税効果が大きくなるといえるでしょう。所得が増えるほど、法人化のメリットをより実感しやすくなります。
経費計上範囲が広がり節税効果が高まる
マンション経営を法人化するメリットとして、経費と認められる範囲が広がる点も見逃せません。個人事業主の場合よりも、多くの費用を経費として計上できるようになるため、課税所得を減らせます。
具体的には、固定資産税などの各種税金や融資の利息、減価償却費に加え、以下のような費用も経費として認められます。
- 管理会社への接待費や贈答費など
- 物件視察や打ち合わせなどに必要な交通費やガソリン代など
- 事業に必要な情報収集のための書籍代
- 車両購入費や維持費など
- 経営者の生命保険料
このような費用を細かく計上することで、節税効果を高めることが可能です。
役員報酬で所得分散が可能になる
マンション経営を法人化すると、家族で家賃収入を分散させて節税効果を高めることができます。
法人を設立してマンション経営を行なう場合、家賃収入はすべて法人に帰属します。これはマンションの名義が法人であるためです。このとき家族を法人の役員にすることで、役員報酬の支払いが発生します。
役員報酬は法人の経費として計上できるため、法人の課税所得を抑えることが可能です。さらに、これまでご自身の所得であった家賃収入が、家族それぞれの所得として分散されることで、一人ひとりの所得税率を下げられます。
所得を分割して所有者の所得税率を下げることで、世帯全体の税負担を軽減できるというメリットが生まれるのです。
相続税対策として活用できる
マンション経営の法人化は、相続税対策にもなります。
まず、将来相続人となる家族を法人の役員や従業員にすることで、マンション経営で得られる所得を報酬としてそれぞれに支払うことが可能です。これにより、家族への支払いが贈与に該当しなくなります。
それとともに、家賃収入が経営者個人の財産として蓄積されるのを防ぎ、相続税の課税対象となる資産の増加を防げるのです。
また、法人がマンションを所有している場合に取得から3年が経過すると、株式評価における不動産の価値は、原則として時価ではなく「相続税評価額」となります。相続税評価額は時価よりも低くなる傾向にあり、結果として相続の対象となる株の評価額も下がるため、相続税を抑えることにつながります。
マンション経営を法人化するデメリット
マンション経営を法人化する4つのデメリットは、以下のとおりです。
- デメリット① 初期設立費用と毎年の維持コストがかかる
- デメリット② 会計・税務処理が複雑化する
- デメリット③ 法人住民税の均等割が必ず課税される
- デメリット④ 不動産売却時の税負担が重くなる可能性がある
マンション経営の法人化には、初期費用の負担・会計処理の複雑化・法人特有の税金・不動産売却時の税負担など、4つのデメリットがあります。
初期設立費用と毎年の維持コストがかかる
マンション経営を法人化する際は、設立費用と毎年の維持費用が発生します。
まず、法人を設立するには法律上の手続きが必要となり、その際に登録免許税・定款認証手数料(合同会社の場合は不要)・定款謄本手数料などの費用が発生します。目安として、株式会社設立には約22万円、合同会社設立には約10万円が必要です。
さらに法人設立後も、法人の規模や利益に応じてさまざまな維持費用がかかります。例えば、税務処理や決算申告を顧問税理士へ依頼する場合は、報酬として年間20万~30万円以上かかるのが一般的です。また、従業員を雇用した場合には社会保険料の支払いも必要となります。
個人経営にはなかったこれらの費用が、法人化による収益を圧迫することがないか、事前に検討しておきましょう。
会計・税務処理が複雑化する
マンション経営を法人化すると、会計処理や税務申告が複雑になり、事務的な負担が重くなる点に注意が必要です。
個人事業主の場合、青色申告を行なう際に複式簿記での記帳を求められます。しかし、法人の場合はさらに厳密な会計処理が求められます。具体的には、日々の取引を詳細に記録する帳簿の作成に加えて、年に一度の決算申告などを行なわなければなりません。
こうした複雑な会計・税務処理には、専門的な知識が求められます。簿記や会計に詳しい人材が社内にいない場合は、税理士へ依頼することになるでしょう。
前述のとおり、顧問税理士への報酬は年間で20万~30万円以上かかるのが一般的です。この費用は恒常的にかかる法人の維持費となるため、費用対効果を事前に検討しておく必要があります。
法人住民税の均等割が必ず課税される
法人住民税は、赤字(利益が出ていない状態)であっても必ず課税される税金です。
個人事業主の場合、事業が赤字であれば住民税の支払いは発生しません。しかし、法人には赤字決算であっても、法人住民税の均等割を支払う義務があります。
均等割は都道府県民税が2万円から、市町村民税が5万円から設定されており、資本金の額や従業員数などによって税額が異なります。そのため、最低でも年間7万円の支払いが発生し、法人経営における固定コストとして大きな影響をおよぼすのです。
参考:法人住民税|総務省
不動産売却時の税負担が重くなる可能性がある
マンション経営を法人化すると、将来的に不動産を売却する際の税負担が、個人事業主より高くなる可能性があります。
個人の場合、不動産売却にかかる税金の税率は所有期間によって異なります。
売却した年の1月1日の時点で所有期間が5年以下の場合、短期譲渡所得となり、所得税と住民税を合わせて39%の税率が適用されます(復興特別所得税を除く)。しかし、所有期間が5年を超える場合、長期譲渡所得となり、税率は所得税と住民税を合わせて20%です(復興特別所得税を除く)。
これに対して、法人が不動産を売却する際の税率は、所有期間にかかわらず法人の実効税率の約35%です。したがって、所有期間が5年を超える不動産を売却する場合は、個人より法人の税率のほうが高くなります。
上記で紹介したように、法人化にはデメリットも存在しますが、年間の不動産所得が800万円を超える場合は法人化により税率軽減の恩恵を受けられます。長期的な視点で考えると、初期費用や会計処理の負担を上回るメリットが得られる可能性が高いでしょう。
土地活用のご相談、まずはお気軽に。相談から物件管理まで一貫したサポートを提供。
法人化の際の会社形態の選び方
法人化の際の会社形態を選ぶ場合には、以下の2つのポイントに注意が必要です。
- 注意点① 株式会社と合同会社、どちらが最適か検討する
- 注意点② 資本金額は税務上、与える影響を考えて決定する
マンション経営の法人化において、選択できる会社形態はいくつかあります。ここでは、株式会社と合同会社の概要や特徴、適している状況、そして資本金額が税務に与える影響について解説します。
株式会社と合同会社、どちらが最適?
マンション経営を法人化する際、選択できる会社形態はおもに、株式会社・合同会社・合資会社・合名会社の4種類があります。
このうち、多くの方が選択するのは「株式会社」か「合同会社」です。これは、どちらも出資者が負う責任が「有限責任」に限られるためで、万一会社が倒産しても出資した金額以上の責任を負うことはありません。
株式会社と合同会社のどちらを選ぶか迷う場合は、合同会社から始めることをおすすめします。設立にかかる費用は、株式会社が約22万円であるのに対し、合同会社は約10万円です。また、合同会社には株主総会や取締役会の開催義務がないため、運営コストも抑えられます。出資者が直接経営に関与するため、意思決定が柔軟であるのもメリットです。
ただし、合同会社は株式会社に比べて社会的信用度が低い傾向があります。金融機関からの評価に影響が出て、銀行口座の開設や融資の面で不利になる可能性があることも考慮しましょう。
資本金額の決定方法は?
マンション経営を法人化する際の資本金は、マンション投資における自己資金に相当します。資本金は建築費の4割程度であるのが理想的です。3割を自己資金、残りの1割を諸経費(不動産取得税など建築費の5%程度)と予備費にあてられます。
ただし、資本金額は高く設定しすぎないよう注意が必要です。資本金が1,000万円を超えると、法人住民税の均等割が最低額の7万円から増額され、税負担が増します。
また、資本金の額は税務に大きな影響を与えます。以下のような税制を理解し、ご自身の事業計画にとって最適な資本金額を決定しましょう。
「消費税の免税事業者制度」
この制度によって、新規法人は原則として1期目と2期目が消費税免税事業者となります。しかし、資本金が1,000万円以上の場合は、設立当初から課税事業者となります。
「中小企業向け優遇税制」
資本金が3,000万円以下の法人を対象に、税額控除が受けられる「中小企業経営強化税制」「中小企業投資促進税制」などがあります。
マンション経営の法人化に必要な手続きと流れ

法人化に必要な手続きと流れは、以下のとおりです。
- ①準備事項を確認して法人を設立する
- ②個人所有物を法人へ移行する
- ③必要に応じて専門家に相談する
マンション経営の法人化には、さまざまな手続きが必要です。ここでは、法人化に必要な手続きの概要と流れを解説します。
なお、法人化手続きの完了までにかかる期間は、合同会社であれば最短2~3週間、株式会社でも最短3週間~4週間ほどです。マンションの建設と併せて法人化を考えている場合は、建築の提案と並行して手続きを進めるとよいでしょう。
準備事項を確認して法人を設立する
法人設立までの手続きには、おもに5つのステップがあります。
ステップ1:会社概要の決定
会社設立前に、会社形態(株式会社か合同会社か)・商号(会社名)・事業目的・資本金・役員構成といった基本事項を決定します。会社形態と資本金の決め方は前述のとおりです。
商号は、すでに同じような商号の会社がないか確認してください。不正競争防止法に触れると、トラブルになる可能性があります。また、ご家族に所得を分散したい場合は、役員に加えることを検討しましょう。
ステップ2:定款(ていかん)の作成
会社のルールブックとなる定款を作成します。定款には、ステップ1で決めた商号、事業目的、資本金、役員構成などを記載します。
ステップ3:定款の認証
作成した定款は公証人役場に提出し、認証を受けなければなりません。電子定款で提出すれば、通常4万円かかる印紙代が不要になります。なお、合同会社の場合、定款認証の手続きは不要です。
ステップ4:資本金の払い込み
発起人または設立時取締役の銀行口座に、出資金を払い込みます。これが会社の資本金となります。
払い込み後に銀行で残高証明書を発行してもらい、預金通帳のコピーをとりましょう。ネット銀行を利用している場合は、払い込んだ事実がわかるページを印刷すれば問題ありません。
ステップ5:会社設立の登記申請
最後に、法務局へ会社設立の登記申請書を提出します。この際、定款や資本金の払込証明書類(銀行の残高証明書や預金通帳のコピーなど)を添付します。
登記完了証が交付され、登記事項証明書が発行されるまでには、通常1~2週間程度かかるのが一般的です。これらの手続きが完了することによって、法人が正式に登記されます。
個人所有物件を法人へ移行する方法
すでに個人で所有しているマンションを法人へ移行する方法には、現物出資・売却・賃貸借などがあります。
これらの方法には、それぞれ以下のような注意点があります。
<法人へ移行する際の注意点>
| 賃貸借 | マンションがオーナー様個人の手もとに残るため、法人化による節税効果は限定的 |
| 売却 | 相続税対策を考えた場合に、現物出資よりも税負担が高くなりやすい |
| 現物出資 | 会社法上の要件を満たす必要があり、検査役による検査や証明が必要になるなど、手続きが煩雑になる |
ご自身の状況や目的に合わせて、最適な移行方法を検討してください。
専門家の選び方と相談するポイント
マンション経営の法人化には専門的な知識が必要です。税理士や司法書士といった専門家にサポートを依頼する際は、まず不動産に関する税制や法律、会計に詳しいことを確認しましょう。
豊富な業務経験を持ち、具体的な提案力や説明力のある専門家を選ぶことが重要です。また、相談しやすい柔軟な対応時間があるか、そしてご自身と相性の良い担当者であるかも大切なポイントです。
税理士へ支払う費用の目安は、以下のとおりです。
| 月額顧問料 | 1万5,000~3万円程度 |
| 決算・確定申告のみ | 5万~10万円程度 |
| 記帳代行・書類整理 | 年10万円程度 |
年間家賃収入が1,000万円を超える場合は、さらに費用が高くなることもあります。
なお、マンション建設と同時に法人化を検討している場合は、まず建築会社に相談してみるのもよいでしょう。
生和コーポレーションのマンション経営サポート
生和コーポレーションは、長年の実績とノウハウでオーナー様のマンション経営をサポートし、成功へ導くサービスをご提供します。
その一つ、最長35年間マンションを一括で借上げるシステム「FG35」は、空室や家賃滞納のリスクを大幅に軽減します。さらに、「24時間365日、専門スタッフによる入居者対応」や「長期にわたる建物無料点検」などにより、物件の資産価値の維持にも貢献。安定したマンション経営を実現いたします。
まとめ:マンション経営の法人化については生和コーポレーションにご相談を
マンション経営の法人化は、税制面で大きなメリットがある一方で、初期費用や会計処理の複雑化といったデメリットをともないます。ご自身の年収や物件規模、メリット・デメリットを総合的に考慮したうえで、法人化するかどうかを慎重に検討しましょう。
生和コーポレーションは、土地活用において50年以上の実績があり、賃貸経営のサポートや賃貸物件の企画・設計・施工などをトータルで行なっています。マンション経営の法人化についてお悩みのオーナー様は、ぜひご相談ください。
他の「失敗しないマンション経営」の記事を見る
-
 マンション経営においては、誰もが「経営に失敗したくない」「赤字になりたくない」と考えるでしょう。 マンション経営の赤字は、「問題ない赤字」と「対処が必要な赤字」に分けられます。後者の状態になってしまっ…
マンション経営においては、誰もが「経営に失敗したくない」「赤字になりたくない」と考えるでしょう。 マンション経営の赤字は、「問題ない赤字」と「対処が必要な赤字」に分けられます。後者の状態になってしまっ… -
 サラリーマンなど給与所得を受けている人は、勤めている会社が税務処理を行ってくれるため、自分では何もする必要がありません。しかし、アパート経営・マンション経営をはじめて、給与所得とは別に年間20万円以上…
サラリーマンなど給与所得を受けている人は、勤めている会社が税務処理を行ってくれるため、自分では何もする必要がありません。しかし、アパート経営・マンション経営をはじめて、給与所得とは別に年間20万円以上… -
 アパート経営・マンション経営はしっかり対策を講じることで高い相続税対策の効果が得られます。近い将来に土地の相続を予定している人にとっては、アパート経営・マンション経営を行うことで相続税対策になることは…
アパート経営・マンション経営はしっかり対策を講じることで高い相続税対策の効果が得られます。近い将来に土地の相続を予定している人にとっては、アパート経営・マンション経営を行うことで相続税対策になることは… -
 アパート経営・マンション経営を始めると、たとえ小規模でも確定申告をして納税する義務が生じます(給与所得者で不動産所得が年間20万円以下の場合など、条件によっては免除されることもあります)。 確定申告は…
アパート経営・マンション経営を始めると、たとえ小規模でも確定申告をして納税する義務が生じます(給与所得者で不動産所得が年間20万円以下の場合など、条件によっては免除されることもあります)。 確定申告は… -
 固定資産税は、土地・家屋・有形償却資産に課税される地方税です。マンション経営をはじめると、土地と家屋(マンション)を所有することになるため、必ず固定資産税が課税されます。 そこで今回は、マンション経営…
固定資産税は、土地・家屋・有形償却資産に課税される地方税です。マンション経営をはじめると、土地と家屋(マンション)を所有することになるため、必ず固定資産税が課税されます。 そこで今回は、マンション経営…