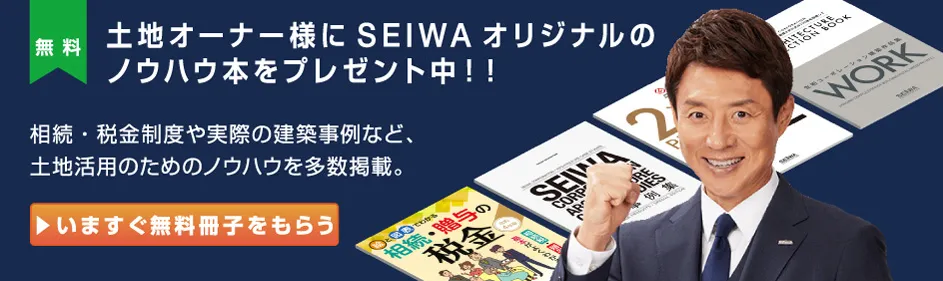不動産投資における「利回り」は物件の収益性 を示す指標であり、投資判断の基準として用いられます。これから不動産投資を始めるにあたり、利回りの高い物件を選びたいとお考えの方もいるのではないでしょうか。
ただし、利回りが高ければ多くの収入を得られるわけではありません。不動産投資を成功に導くには表面利回り・実質利回り・想定利回り・現行利回りの違いを把握するとともに、立地や建物の構造、築年数、運営コストなどを総合的に考慮することが大切です。
本記事では、土地活用で半世紀以上の実績を持つ生和コーポレーションが、利回りの種類や計算方法、変動要因、高利回り物件に潜むリスク、安定した不動産投資を実現するためのポイントについて紹介します。
この記事の目次
不動産投資における利回りの種類
不動産投資で用いる利回りの種類は以下の4つです。
- 表面利回り
- 実質利回り
- 想定利回り
- 現行利回り
不動産投資における「利回り」とは、物件の取得費に対して、年間でどれだけの家賃収入が得られるかを示す指標です。投資物件の収益性を判断するうえで欠かせない概念であり、計算方法によって「表面利回り」「実質利回り」「想定利回り」「現行利回り」のおもに4種類に分けられます。
なお、前提として、所有している土地に建物を建てて運用する場合は「建物」、購入した土地に建物を建てる、あるいは中古物件を購入して運用する場合は「土地と建物」が利回りの対象となることを押さえておきましょう。
ここでは、各利回りの特徴、注意点について解説します。
表面利回り
表面利回りとは、物件価格に対する年間の家賃収入の割合です。
表面利回りを求める際には、投資物件の維持にかかる管理費や固定資産税、修繕費などの経費は一切考慮しません。そのため、実際の利回りと比べ、数字が高くなるのが特徴です。
不動産投資の広告では、表面利回りが用いられる傾向にあります。利回りの高さに飛び付くと思うような収入を得られないこともあるため、後述する実質利回りも併せて検討することが大切です。
なお、中古物件の表面利回りは現実の数字となるため後述する想定利回りとは異なりますが、新築物件の場合は表面利回りと想定利回りが同じように扱われる場合があるため注意が必要です。
実質利回り
実質利回りとは、年間の家賃収入から諸経費を差し引いた数字を、物件価格と購入時にかかった経費を足したもので割って算出される割合のことです。
経費を考慮しない表面利回りに対し、実質利回りの数字は低くなるのが一般的です。物件の収益性を正確に把握できるため、投資物件を選ぶときには実質利回りを重視するとよいでしょう。
想定利回り
想定利回りとは、一棟アパートや一棟マンションの賃貸経営において、住戸が「満室」の状態を想定した割合のことです。
想定利回りを求めるときには、空室や家賃の下落といったリスクは考慮されません。したがって空室が一つでも発生すれば、実際の利回りは想定利回りよりも低くなります。
現行利回り
現行利回りとは、現在の入居者から得られる家賃収入をもとに算出した割合のことです。計算式は「(実際に入居者から得られる年間家賃収入÷物件価格)×100」で、入居者のいない部屋の家賃は反映されません。
空室状況を反映させているため、想定利回りと比べて現実的な収益率を把握できる点が特徴です。
ただし、現行利回りは実質利回りと異なり経費を考慮しないため、正確な収益率を把握するのは難しいといわざるを得ません。そのため、投資物件を比較・検討する際には現行利回りだけでなく、実質利回りにも着目するとよいでしょう。
不動産投資で知っておきたい利回りの計算方法
不動産投資における利回りの計算方法は以下のとおりです。
- 表面利回りの計算方法
- 実質利回りの計算方法
- 想定利回りの計算方法
不動産投資における利回りは、投資物件の収益性を判断するための重要な数値です。計算方法を正しく理解しておくことで、物件同士の比較や投資判断がしやすくなります。
ここでは、実際の不動産投資で用いられる「表面利回り」「実質利回り」「想定利回り」の計算方法について紹介します。
表面利回りの計算方法
表面利回りは、「年間に得られる家賃収入÷物件価格×100」の計算式で求められます。前述のとおり、表面利回りは諸経費を考慮しないため、計算式も非常にシンプルです。
実質利回りの計算方法
実質利回りは表面利回りと異なり、家賃収入からかかった諸費用を差し引いて求めます。計算式は「(年間に得られる家賃収入-年間にかかる諸費用)÷(物件価格+購入時にかかった諸費用)×100」です。
実質利回りの計算時に用いる諸費用には、おもに以下のものがあります。
- 物件購入時にかかった費用(仲介手数料、不動産取得税、登録免許税、印紙代、司法書士の報酬など)
- 修繕費・修繕積立金
- 水道光熱費
- 固定資産税・都市計画税
- 火災保険料
- 賃貸管理委託料
- 入居準備費用(鍵の交換費用、部屋の清掃費用など)
また、実質利回りを計算するときは、毎月支払う費用だけでなく、突発的な修繕費などイレギュラーで発生する費用も含めて計算するのがポイントです。費用の洗い出しには手間がかかりますが、正確な投資判断をするためには、より現実的な利回りを求めたうえで投資物件を検討することが大切です。
想定利回りの計算方法
想定利回りは、「満室時の年間家賃収入÷物件購入価格×100」の計算式で求めます。
投資物件を紹介する広告に記載される利回りは、表面利回りに加え、想定利回りが使われるケースもあります。実際には空室リスクや家賃下落リスクがあるため、数字をそのまま信じず、現況やエリアにおける賃貸需要も併せて確認することが重要です。
不動産投資の利回りが変わる6つの要素
建物の築年数や立地など、利回りに影響する要素は以下のとおりです。
- 新築物件の利回りは購入価格で変動する
- 購入価格が安い中古物件は利回りが高くなりやすい
- 建物の種類による利回りの違い
- 物件の構造による利回りの違い
- 立地やエリアによる利回りの違い
- 一棟の建売とランドセットによる投資方法の違い
不動産投資の利回りは、物件の築年数や建物の種類、構造、立地条件などの要因で変動します。投資物件選びの失敗を回避するためにも、どのような要素が利回りに影響するのかを把握しておきましょう。
新築物件の利回りは購入価格で変動する
新築物件は中古物件と比べて需要が高く、空室リスクは低くなる傾向です。家賃も周辺相場より高く設定できるため、より多くの収入を得られる可能性があります。
また、新築物件は購入価格が高くなるため、同じ立地条件の中古物件と比べて表面利回りが低くなるケースが一般的です。ただし利回りが低くても、新築物件は最新の設備や耐震性の高さから、当面の間は修繕の必要性がありません。
修繕に関する費用を抑えられるため、購入価格が高くても、長期的な運用によって安定した収入を得ることも可能です。
購入価格が安い中古物件は利回りが高くなりやすい
中古物件は購入価格が安いため、新築物件と比べて利回りが高くなることが一般的です。立地や間取りなどの条件が良い物件を購入できれば、少ない投資額で効率良く収入を得られます。
ただし、築年数の古い中古物件は目には見えない構造部分が劣化していたり、設備の老朽化が進んでいたりする可能性があります。修繕や設備の交換などの追加費用が発生しやすいため、中古物件を選ぶ場合は修繕履歴や管理状況を確認するようにしましょう。
建物の種類による利回りの違い
不動産投資の対象となる物件は、一棟マンション・一棟アパート・区分マンション・一戸建てに大きく分けられます。
一棟のマンションやアパートは初期費用が高額な反面、複数の住戸から家賃収入を得られる点がメリットです。空室リスクを軽減できるため経営の安定性が高く、利回りも高い傾向があります。
区分マンションとは、一棟のマンションのうちの1室のことです。一棟マンション・アパートよりも初期費用を抑えられる分、土地を持たない方や企業勤めの方でも始めやすい点がメリットです。ただし、収入源が1室のみに限定されるため、一棟投資よりも利回りは低くなる傾向にあります。
一戸建ての物件はファミリー層からの需要が期待できるため、入居期間が長期化する傾向にあります。郊外にある一戸建てでもペットの飼育可能・駐車場付きなどの付加価値を提供すると入居者が見つかりやすく、安定した賃貸経営が可能です。
ただし、一戸建ては一世帯しか入居できないため、空室リスクが非常に高くなります。入居者が退去すると家賃収入がゼロになり、集合住宅のようにほかの入居者から収入を得られないためです。
物件の構造による利回りの違い
利回りは立地や入居率だけでなく、建物の構造によっても変動します。構造の違いは建築費、耐用年数、家賃水準、資産価値など、収益性に直結する要素へ影響を与えるためです。
賃貸物件の構造はおもに木造、鉄骨造、RC(鉄筋コンクリート)造の3種類です。
木造はアパートに多い構造で、建築費が比較的安く、初期投資を抑えられます。同じ家賃収入でも、初期費用を抑えられる分、表面利回りが高く出やすいのが特徴です。
RC造は木造よりも建築費が高額になるため、「家賃が同じ」という条件なら木造の利回りが高くなります。一方、立地が同じならRC造の家賃が高くなり、建物の規模が同じであれば木造の建築費が安くなります。
ただし、木造はRC造と比べて耐用年数が短く、劣化を防ぐには定期的なメンテナンスも欠かせません。
鉄骨造は、中層マンションで採用されることが多い構造です。木造よりも建築費は高くなりますが、耐用年数が長く、家賃もやや高めに設定できます。
建築費や耐用年数は木造とRC造の中間に位置するため、利回りと安定性の両立を図れる構造といえます。
RC造は、おもに大型マンションで用いられる構造です。建築費は最も高額ですが、耐用年数が長く劣化しにくいため、資産価値を維持しやすい点が特徴です。初期費用が高いこともあり、当初の利回りは低めに出ますが、長期的な運営により安定した収入が見込めます。
立地やエリアによる利回りの違い
物件が建つ立地も、利回りに大きな影響を与えます。
例えば都市部にあるマンション・アパートの場合は、人口が多いことで賃貸需要が高く、空室リスクが低い傾向にあります。その反面、地方と比べて物件価格が高く、利回りは低めに出ることが一般的です。
一方、地方は物件価格が安いため、利回りは高くなる傾向です。ただし、人口が減少している地域にあるマンション・アパートは、都市部よりも空室リスクが高くなります。
なお、自身が所有する土地にマンションを建築して運用する場合の建築費は、都市部でも地方でも大きくは変わりません。しかし都市部のほうが家賃を高く設定できる分、結果的に利回りが高くなる傾向です。
一棟の建売とランドセットによる投資方法の違い
従来、一棟マンションの不動産投資は、開発済みの土地に建てられた建売マンションを購入する方法が主流でした。近年は、購入した土地に新築のマンション・アパートを建築して運用する「ランドセット」と呼ばれる手法で不動産投資を行なう方も少なくありません。
ランドセットのメリットは、土地を所有していなくても不動産投資を始められることです。
まず土地の購入から始めるため、賃貸需要の高いエリアを選択できます。加えて、土地に建てるマンション・アパートの間取りや仕様を自分で決めることも可能です。さらに、市場相場より割安な価格で土地を購入できれば、初期費用を抑えられて利回りが有利になる可能性もあります。
ただし、ランドセットで不動産投資をするには、自己資金が潤沢でないと難しいのが実情です。ランドセットによる不動産投資では金融機関の融資を利用して土地の購入費用、マンション・アパートの建築費用を賄うケースが一般的で、資産背景がしっかりしている方でないと成り立たないとされています。
ランドセットによって不動産投資を始めたいと考えている場合は、資金計画や資産状況を踏まえて慎重に検討することが大切です。
不動産投資の理想的な利回りと最低ラインとは?
前述のとおり、不動産投資の利回りは、利回りの種類、建物の築年数、立地、建物の種類や構造など、複数の要素によって変動します。例えば、物件価格が同じでも、立地条件が良ければ家賃を高く設定でき、利回りの面でも有利になります。
物件タイプ別の利回りの相場は、以下の表のとおりです。
| 物件タイプ | 表面利回りの相場 | 特徴 |
|---|---|---|
| 一棟マンション | 新築:3~5%程度
中古:7~12%程度 |
|
| 一棟アパート | 新築:5%程度
中古:5~10%程度 |
|
| 区分マンション | 新築:3~5%程度
中古:5~8%程度 |
|
| 一戸建て | 新築:5~6%程度
中古:6~8%程度 |
|
ただし、上記の利回りはあくまでも目安であり、地域や物件条件などによって数字は変動します。したがって、「不動産投資で収入が出る利回りの最低ラインは◯%」などの明確な基準は存在しません。
さらに、利回りが高ければ良いわけではない点にも留意が必要です。不動産投資を成功させるには賃貸需要は期待できるか、将来的にどのくらいの維持費・修繕費が必要になるかなどを考慮し総合的に判断することが欠かせません。経営の安定性を重視する場合は、多少利回りが低くても空室リスクの低い物件を選ぶことが理想です。
土地活用のご相談、まずはお気軽に。相談から物件管理まで一貫したサポートを提供。
「高利回り」の不動産投資に潜むリスク
利回りの高さは、投資物件を選ぶ際の基準の一つとなります。しかし不動産投資を始めるにあたり、利回りの高さだけを意識するのは危険です。
そもそも利回りが高くなるのは、物件の購入価格が安い、または年間の家賃収入が高い物件です。
価格が安い物件は、築年数が経過している、立地が悪いなど、条件が良くないケースも少なくありません。特に、築年数の古い物件は運用に際して多額の修繕・リフォーム費用がかかるため、想定される利回りを大きく下回る可能性がある点に注意が必要です。
また空室になると、家賃収入が途絶える一方で維持費や融資の返済などの支払いは発生し続けて手元にお金が残らなくなるリスクもあります。
高利回りの物件は魅力的に見えますが、「利回りが高い=多くの収入を得られるとは限らない」のです。そのため、不動産投資を成功させたいなら、利回りの高さだけでなく立地条件や賃貸需要の有無、将来かかると予測されるランニングコストなどをしっかりと確認することが大切です。
不動産投資の成功とは?利回りより安定性を優先すべき理由
不動産投資における成功の定義、利回りに固執すべきでない理由としては以下が挙げられます。
- そもそも不動産投資の成功に定義はない
- 需要が高いエリアの物件は低利回りでも収入が安定する
- 物件時の利回りが続くことはほぼない
不動産投資で理想とする収入を得るには、利回りに振り回されないこと、安定した運用を続けることが大切です。ここでは、不動産投資における成功の考え方、利回りよりも安定性が必要な理由について解説します。
そもそも不動産投資の成功に定義はない
不動産投資に取り組む目的は人によって異なります。そのため、何をもって「成功」と定義するかは一概にはいえません。
例えば、毎月安定した家賃収入を得ることを成功と考える方がいれば、老後の資産形成や相続対策、所得税の節税などを目的とする方もいるでしょう。また、成功と感じる収入の金額や達成基準も、個々の投資家によって異なります。
したがって不動産投資を始める際には利回りという指標に固執するのではなく、自分が何を得たいのかを明確にすることが重要です。目的を定めることで、物件選びの指標や運用方針も定まり、結果として満足度の高い投資につながります。
需要が高いエリアの物件は低利回りでも収入が安定する
不動産投資では、物件の立地が得られる家賃収入の安定性を大きく左右します。
ただし、都市部や人気の高い住宅地、最寄り駅に近い立地など、賃貸需要が高いエリアにある物件は購入価格が高くなります。その分、表面利回りも低めに出る傾向です。
一方で、空室リスクが低く、長期間安定した家賃収入を得やすい強みがあるのも事実です。さらに、賃貸需要が高い物件は売却時にも買い手が付きやすく、将来的に現金化しやすいメリットもあります。そのため、安定した賃貸経営を行ないたいのなら、利回りが低くても賃貸需要の高いエリアにある物件を選択することがポイントです。
物件購入時の利回りを維持するのは難しい
物件購入時の利回りが高かったからといって、当初の数字を長期間維持できるとは限りません。
不動産は日々価値が変動する資産であり、建物や設備は年数とともに劣化します。加えて、周辺環境や賃貸需要の変化、修繕費や税金の増加など、利回りを押し下げる要因も多く存在します。
そのため、当初の利回りだけを根拠に購入を判断すると、想定どおりの収入を確保できなくなる可能性がある点に注意が必要です。不動産投資を成功させたいのなら、利回りは変動するものであると理解し、物件の取得時から長期経営を見据えた計画を立てることが重要です。
例えば、事前に事業計画書を作成し、想定される家賃収入と必要経費を考慮したうえで借入金を無理なく返済できるかシミュレーションする方法があります。利回りの変動や空室リスクを考慮した事業計画を立てておくと、より堅実で安定した賃貸経営を行なえるようになります。
ただし、インフレが続くと建築費や人件費などのコストが上昇し、家賃も継続的に上がる傾向にあります。インフレ時に事業計画をシミュレーションする場合、建築費の動きや金利の上昇などの変動を考慮することが大切です。
土地購入&土地活用による不動産投資は生和コーポレーションへ
生和コーポレーションにおける不動産投資の成功事例として、以下2つを紹介します。
- 土地購入&マンション経営で節税と資産運用を両立
- 築50年の空き家を3階建の木造マンションに建て替え
生和コーポレーションは、賃貸物件の建設や管理などの土地活用事業を主力とする企業です。実際に生和コーポレーションのサポートで不動産投資を成功させた、2件の事例を紹介します。
土地購入&マンション経営で節税と資産運用を両立
大阪府東大阪市にお住まいのオーナー様が、ランドセットの手法で賃貸マンションを建設した事例です。
オーナー様は所有する土地の活用ではなく、ランドセットの手法によって不動産投資を開始しました。会社の事業として融資を受けることで、節税対策と資産運用を両立できると考えたのがその理由です。
賃貸マンションの建築会社として生和コーポレーションを選択したのは、長年の実績やノウハウ、資金計画のサポート力、営業担当者の誠実で迅速な対応が決め手だったといいます。
完成したマンションには、外壁の汚れを軽減する光触媒を採用するなど、細部にまでオーナー様のこだわりが反映されています。
満室経営を実現できた今回の成功を受け、現在は2棟目の賃貸マンションの建設にも着手。長期にわたって安定した家賃収入を得られる基盤作りに成功したケースです。
築50年の空き家を3階建ての木造マンションに建て替え
東京都大田区で、先々代から受け継いだ築50年の空き家を木造3階建て賃貸マンションに建て替えた事例です。
オーナー様は過去に不動産の相続で大変な思いをした経験から、相続対策として空き家の建て替えを検討していました。営業担当者の誠実な人柄、住まいまで何度も訪れて収支計画から相続税対策まで丁寧に提案する姿勢が生和コーポレーションを選んだ決め手だったそうです。
木造は騒音や寒さが気になるというイメージを覆し、完成したマンションは遮音性や断熱性に優れ、木造とは思えない快適な住環境を実現しました。また、大通り沿いに位置するため、周囲の環境に調和する外観にこだわったといいます。高級感のあるデザインにしたところ、瞬く間に満室になったことに驚いたそうです。
またサブリース契約により、入居者の募集から建物の管理まですべて生和コーポレーションが行なうため、オーナー様自身の手間がかからない点もメリットです。
まとめ:不動産投資は利回りだけで判断せず安定性を意識しよう
不動産投資の利回りは収益性を判断する重要指標ですが、広告にある表面利回りや想定利回りだけでは実際の収入と差が生じることがあります。
そのため経費を含めた「実質利回り」を重視することが大切です。また、空室や修繕費による収益低下も想定されるため、利回りの高さだけで物件を選ぶのは危険です。特にランドセットでの投資は長期的な事業計画が成功の鍵となります。
生和コーポレーションでは資金計画の作成からマンションの建築、賃貸経営まで、土地活用に関するさまざまなサポートを提供しています。土地活用やランドセットによる不動産投資をご検討の方は、生和コーポレーションにご相談ください。
他の「土地活用方法・検討のポイント」の記事を見る
-
 RC造は、主要構造部や基礎が鉄筋とコンクリートで造られている構造です。耐火性や耐震性、耐久性などに優れていることから、低層~中高層の賃貸マンションやビル、戸建て住宅など多くの建造物に採用されています。…
RC造は、主要構造部や基礎が鉄筋とコンクリートで造られている構造です。耐火性や耐震性、耐久性などに優れていることから、低層~中高層の賃貸マンションやビル、戸建て住宅など多くの建造物に採用されています。… -
 「土地を借りて家を建てたい」、あるいは「土地を貸して収入を得たい」と考えているものの、「借地権の仕組みが複雑でよくわからない」「契約時に注意すべき点を知りたい」といった疑問をお持ちの方もいるのではない…
「土地を借りて家を建てたい」、あるいは「土地を貸して収入を得たい」と考えているものの、「借地権の仕組みが複雑でよくわからない」「契約時に注意すべき点を知りたい」といった疑問をお持ちの方もいるのではない… -
 不動産を取得すると、固定資産税や都市計画税、不動産取得税といった税金がかかります。特にマンションやアパート経営を始める際は、こうした税金を事業計画に組み込むことが欠かせません。 また、節税を目的に賃貸…
不動産を取得すると、固定資産税や都市計画税、不動産取得税といった税金がかかります。特にマンションやアパート経営を始める際は、こうした税金を事業計画に組み込むことが欠かせません。 また、節税を目的に賃貸… -
 マスターリースは「一括借上げ」とも呼ばれている賃貸物件の契約形態です。サブリース会社が物件のオーナー様から物件を一棟全体借り上げ、その物件を入居者に転貸することで賃料収入を得ます。 マスターリースには…
マスターリースは「一括借上げ」とも呼ばれている賃貸物件の契約形態です。サブリース会社が物件のオーナー様から物件を一棟全体借り上げ、その物件を入居者に転貸することで賃料収入を得ます。 マスターリースには… -
 土地のオーナー様のなかには、「店舗付き住宅」に興味がある方もいるのではないでしょうか。店舗付き住宅は、おもに1~2階にテナントが入った賃貸マンションを建てて経営する土地活用方法です。 この記事では、店…
土地のオーナー様のなかには、「店舗付き住宅」に興味がある方もいるのではないでしょうか。店舗付き住宅は、おもに1~2階にテナントが入った賃貸マンションを建てて経営する土地活用方法です。 この記事では、店…