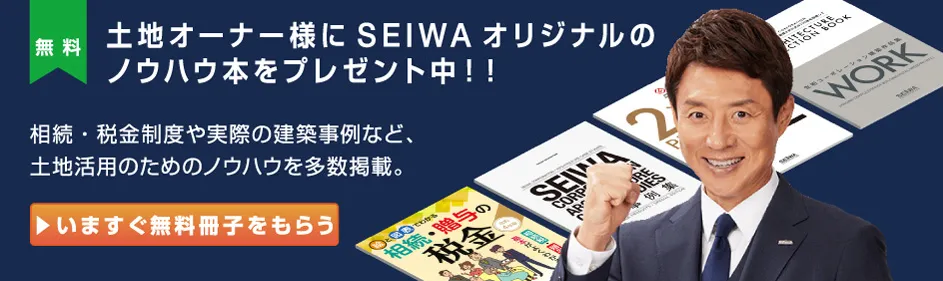不動産の売買や相続、贈与などで所有権の名義が変わる場面では「所有権移転登記」が必要です。しかし、何から始めればよいかわからず、手続きを後回しにする方は少なくありません。
また、税負担や債権者からの差押えを回避したい、権利関係の問題からすぐに着手できないなどの理由で、未登記のまま不動産を放置するケースも見受けられます。
登記を怠った場合には自分が不動産の所有者であることを法的に主張できないだけでなく、不動産活用が滞ったり、手続きが煩雑化したりといった不都合が起こりかねません。トラブルを避けるためにも、不動産を取得した時点で迅速かつ適切に所有権移転登記の手続きを行ないましょう。
この記事では、所有権移転登記の基本的な知識から具体的な手続きの流れ、未登記によるデメリットまで詳しく解説します。
この記事の目次
所有権移転登記とは|不動産の名義を正式に変更する手続き
所有権移転登記とは、不動産の所有者の名義を変更し、誰がその権利を有しているかを明確にする法的な手続きです。これにより、売買や相続などの場面で自分が不動産の所有権を有していることを第三者に証明できるようになります。
所有権移転登記は民法177条で「第三者への対抗要件」として定められているもので、不動産の継承や処分を円滑に進める際には欠かせません。
登記が未了のままだと、万が一二重譲渡が行なわれた場合に自らの所有権を主張できない可能性があります。判例では、登記を先に行なった側が所有権を有するとされているためです。
このように、所有権移転登記は、不動産に関する売買・相続トラブルを避けるうえで重要な防衛策といえるでしょう。
所有権移転登記が必要になる4つのケース
所有権移転登記が必要になる場面は、日常生活のさまざまなタイミングで訪れます。例えば「親から家を相続した」「子どもに土地を贈与した」などで不動産の所有者が変わるケースでは、所有権移転登記の手続きが必須です。
登記を怠ると、将来的に「第三者に対して自分の所有権を主張できない」などのトラブルに見舞われるおそれがあります。トラブルを未然に防ぐためにも、どのケースで所有権移転登記が必要になるかを把握しておきましょう。
ここでは、所有権移転登記が必要となる以下4つのケースについて解説します。
- ケース1不動産を購入・売却した場合
- ケース2:不動産を相続した場合
- ケース3:不動産を贈与で取得した場合
- ケース4:財産分与をした場合
不動産を購入・売却した場合
不動産の売買で所有者が変わったときには、所有権移転登記を行なう必要があります。売買契約だけでは法的な効力は限定的であり、買い主が登記しなければ法的に所有権を取得したとは見なされません。
登記をしないまま放置すると、万が一、売り主が同じ不動産を第三者に売却した場合に自分の所有権を主張できない可能性があります。
さらに、融資の手続きに支障をきたす場合もあるでしょう。例えば、新築や中古住宅の購入時に融資を利用する場合には、抵当権設定登記が不可欠です。抵当権設定登記と所有権移転登記は並行して進められることが一般的で、登記が未了だと融資手続きそのものが進行しません。
不動産購入時の所有権移転登記は、自己の権利を守りスムーズに土地活用をするうえでも重要なステップです。
不動産を相続した場合
被相続人から不動産を受け継いだ場合も、所有権移転登記による名義変更が必要です。登記が完了していないと、その不動産の売却や担保提供、活用などの手続きが進められません。
従来、相続にともなう所有権移転登記(相続登記)は任意でしたが、2024年4月からは相続の発生を知った日から3年以内の申請が義務化されました。正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。相続人同士のトラブルや以降の手続きの煩雑化を避けるためにも、早めの対応が不可欠です。
不動産を贈与で取得した場合
配偶者や子どもなどに不動産を贈与する場合も、所有権移転登記を行なわなければなりません。「贈与登記」とも呼ばれる手続きで、正式には贈与に起因する所有権移転登記です。
贈与登記は法的な義務ではありません。ただし登記を行なわずに贈与者が亡くなると、未登記の不動産が贈与されたものではなく、相続財産の一つと見なされるリスクが発生します。遺産分割の対象となれば、相続人同士での協議が必要となり、状況によっては取得を巡ってトラブルに発展する可能性もあるでしょう。
また、登記を怠って放置すると、第三者が登記してしまった際に、贈与を受けた側が所有権を主張できなくなるおそれもあります。したがって不動産の贈与を受けた場合にも、早めの所有権移転登記が不可欠です。
財産分与をした場合
離婚による財産分与で不動産を取得した場合も、所有権移転登記の手続きが必要です。財産分与にともなう不動産の名義変更には離婚協議書や調停調書などの書類を用意する必要があるほか、当事者双方の立ち会いや同意が求められるケースもあります。そのため、離婚が成立したら速やかに手続きを進めることが重要です。
登記手続きをあと回しにすると、相手が転居・連絡不能になった場合に、名義変更が煩雑になるリスクも生じます。
所有権移転登記をしなかった場合の4つのリスク
不動産の所有権移転登記を行なわずに放置すると、さまざまな法的・実務的なトラブルに発展する可能性があります。手続きを怠った場合に起こり得るおもなリスクは、以下の4つです。
- リスク1 第三者に権利を主張できない
- リスク2 トラブル時に法的保護を受けにくい
- リスク3 相続・売却・融資が滞る可能性がある
- リスク4 固定資産税の負担が続く可能性がある
ここでは、それぞれのリスクを解説します。
第三者に権利を主張できない
不動産の権利関係は、登記によって法的に確定します。そのため、たとえ実際に売買や贈与が成立していたとしても、所有権移転登記が行なわれていなければ、法律上の所有者としては認められません。所有権移転登記を怠っている間に別の第三者が同じ物件に対して登記を行った場合、そちらが優先される可能性があります。
所有権移転登記は単なる手続きではなく、他者に対して所有権を主張するための権利保全の基本です。未登記のままでは、二重譲渡などのトラブル発生時に自分の所有権を主張できず、大きな不都合が生じる可能性が高くなります。安心して不動産を保有するには、適切かつ速やかな登記が不可欠です。
トラブル時に法的保護を受けにくい
登記がされていない不動産は、法律上の所有者としての権利があいまいになります。これにより、裁判や調停などの法的手続きで「誰が正当な所有者か」を証明できず、不利な立場に置かれるケースも少なくありません。
特に相続や離婚など複数の当事者が関与する場面では、登記の有無が重要な争点となりやすく、関係者間のトラブルを招く要因にもなり得ます。第三者との協議において自身の正当性を主張するには、所有権移転登記を適切に行なうことが大切です。所有権を法的に確保し、将来的な資産トラブルを未然に防ぐ観点からも、所有権移転登記はできるだけ早めに済ませましょう
相続・売却・融資が滞る可能性がある
所有権移転登記がされていないと、不動産を売却できません。不動産を売却するときには、必ず司法書士による本人確認が行なわれるためです。登記事項証明書の所有者と売買契約書の売り主が異なっている場合には、契約が無効になってしまいます。そのため、相続した不動産の名義が故人のままだとまずは相続登記の手続きを行なう必要があり、売却までに手間や時間がかかる点がデメリットです。
さらに、登記がない建物には抵当権を設定できないため、建て替えやリフォーム時に融資を受けられないリスクもあります。このように、資産の有効活用を考えている場合、名義が不明瞭な状態では大きな障害となりかねません。将来的な損失を避けるためにも、不動産を取得したときには速やかに所有権移転登記の手続きを行ないましょう。
固定資産税の負担が続く可能性がある
所有権移転登記が済んでいない場合、税務上では引き続き旧所有者が不動産を保有していると見なされます。これにより、たとえ物件を譲渡していても、旧所有者に固定資産税の納付書が届き続ける事態が起こる点にも注意が必要です。
税金に関するトラブルを防ぐには、不動産の譲渡が行なわれた時点で所有権移転登記を完了させることが不可欠です
所有権移転登記にかかる3つの費用項目
所有権移転登記にかかるおもな費用は、以下の3つに分類されます。
- 費用1 登録免許税
- 費用2 司法書士報酬
- 費用3 その他の実費
登記にかかる費用は、原則現金で支払う必要があります。登記手続きをスムーズに進めるためには、事前にどのくらいの費用がかかるのかを把握し準備しておくことが大切です。ここでは、それぞれの費用の目安について解説します。
登録免許税
登録免許税とは、売買や相続、贈与などで不動産の所有権移転登記を行なうときに課される国税です。税額は「固定資産税評価額×所定の税率」の計算式で算出され、税率は登記の原因によって異なります。各ケースにおける税率は以下の表のとおりです。
| 移転理由 | 税率 |
|---|---|
| 売買 | 2%(令和8年3月31日までの間に登記を受ける場合は1.5%) |
| 相続 | 0.4% |
| 贈与 | 2% |
| 財産分与 | 2% |
例えば、固定資産税評価額が5,000万円の土地を相続した場合は税率が0.4%となるため、納めるべき登録免許税は20万円です。一方で、贈与の場合は税率が2%であり、登録免許税は100万円となります。
司法書士報酬
所有権移転登記の手続きを司法書士に依頼する場合、報酬の支払いが発生します。報酬額は物件の種類や登記の難易度、地域によって異なりますが、5万円〜10万円程度が相場です。
報酬には申請書類の作成や登記所への提出、必要書類の取得代行費用などが含まれます。司法書士事務所によって費用は異なるため、事前に見積もりを取って内訳を確認しておくとよいでしょう。依頼内容によって追加費用がかかるケースもあるため、トータルでの費用感をつかんだうえで依頼することが大切です。
その他の実費
所有権移転登記を行なう際には、住民票・印鑑証明書・戸籍謄本などの書類取得費用がかかります。また、登記簿謄本や固定資産評価証明書を取り寄せる際にも数百円~数千円の手数料が必要です。
加えて、交通費や郵送費といった雑費を見込んだうえで費用を準備しておくと安心です。事前に必要書類と費用をリストアップしておき、資金・スケジュールの両面に余裕を持って手続きを進めましょう。
所有権移転登記申請に必要な書類一覧
所有権移転登記を申請する際には、登記の原因や当事者の関係性に応じて、さまざまな書類が必要になります。売買や贈与、相続などケースによって求められる内容が異なるため、あらかじめ必要書類を把握しておくとスムーズです。以下におもな書類とその概要、用意する人を表でまとめました。
| 書類名 | 概要 | 用意する人 |
|---|---|---|
| 登記識別情報/登記済証(権利証) | 現在の所有者を証明する書類 | 売り主・贈与者・相続人 |
| 売買契約書/贈与契約書 | 所有権移転の理由となる契約書 | 売り主・買い主/贈与者・受贈者 |
| 固定資産評価証明書 | 不動産の評価額を証明する書類 | 売り主・贈与者 |
| 委任状 | 司法書士に手続きを委任する場合に必要な書類 | 委任する当事者 |
| 本人確認書類 | 登記申請者の身元確認書類 | 売り主・買い主/贈与者・受贈者 |
| 印鑑証明書 | 実印の証明書(発行から3ヵ月以内) | 売り主・贈与者 |
そのほか、各種書類への押印用に印鑑を用意する必要があります。
土地活用のご相談、まずはお気軽に。相談から物件管理まで一貫したサポートを提供。
所有権移転登記の申請方法2つ
所有権移転登記の申請方法は、大きく分けると以下の2パターンです。
- 司法書士に依頼する
- 自分で申請する
法的には自分で申請可能ですが、正確に手続きを行なうには専門的な知識や経験が必要です。所有権移転登記を確実に、かつスムーズに行なうためにも、経験豊富な司法書士に依頼することをおすすめします。
ここでは、それぞれの方法にかかる費用や手間、メリット・デメリットを解説します。
司法書士に依頼する
司法書士は、不動産の売買や相続、贈与などの際に必要となる登記手続きを専門とする国家資格者です。所有権移転登記も、書類作成から法務局への申請まで一括して任せることができます。申請ミスや書類の不備による手続きの遅延といったリスクが大幅に軽減される点も大きなメリットです。
前述のように、司法書士へ所有権移転登記の手続きを依頼すると5万円~10万円ほどの報酬が必要となります。ただし正確性や安全性を踏まえると、不動産の売買や相続といった重要な局面では司法書士に依頼するのが賢明な判断です。
自分で申請する
法律上は、所有権移転登記を自分で行うことも可能です。専門家への報酬が不要であり全体的な費用が抑えられる点はメリットですが、自力で申請するには登記制度に関する正しい理解と書類作成の知識が求められます。
例えば、記載ミスや添付書類のミスがあると、申請が却下されたり手続きが長引いたりといったリスクが発生しかねません。必要書類の取得にも時間と労力がかかり、仕事や日常生活の合間に進めるのは困難です。
こうした背景を踏まえても、自己申請はあくまでも十分に経験や知識のある方に向いた手段といえます。安全かつ正しく所有権移転登記を行なうためにも、登記手続きの専門家である司法書士に依頼したほうがよいでしょう。
所有権移転登記を進める5つのステップ
所有権移転登記は、司法書士に依頼して進めるケースが一般的ですが、手続きの流れをあらかじめ把握しておくと、必要書類の準備やスケジュール管理がスムーズになります。ここでは、登記完了までの基本的な5つのステップを紹介します。
- ステップ1 登記申請書を作成する
- ステップ2 必要書類を用意する
- ステップ3 法務局に登記申請をする
- ステップ4 書類審査を受ける
- ステップ5 登記完了証を受け取る
ステップ1登記申請書を作成する
登記申請書は、法務局が指定する様式に沿って作成します。物件の所在地や面積、移転理由、登記を行なう当事者の氏名・住所など、正確な情報の記入が必要です。売買、相続、贈与など登記の原因によって書類の様式や記載する内容が異なるため、注意しましょう。
なお、申請書の様式は法務局の窓口で手に入るほか、Webサイトからもダウンロード可能です。
司法書士に依頼する際は、情報提供と記載内容の最終確認を求められるケースもあるので、適切に対応しましょう。正確な申請書作成が、スムーズな手続きの第一歩となります。
ステップ2必要書類を用意する
所有権移転登記では、申請書以外にも複数の書類が必要です。例えば売買による移転であれば、売買契約書・登記識別情報・印鑑証明書・固定資産評価証明書などが求められます。
一方、相続の場合は、被相続人の出生から死亡に至る戸籍謄本や遺産分割協議書なども手配しなければなりません。このように、登記の原因によって用意するべき書類が異なるため、事前に確認しておくと安心です。
書類の一部は司法書士が取得代行してくれますが、登記済証や印鑑証明書など依頼者側での手配が必要なものもあります。申請時に不備が発生しないよう、余裕を持って書類の準備を進めましょう。
ステップ3法務局に登記申請をする
必要書類がすべて整い次第、司法書士が管轄の法務局へ登記申請を行ないます。提出方法は窓口への持参のほか、郵送や「登記・供託オンライン申請システム」を通じた電子申請も可能です。オンライン申請であれば、窓口の時間外でも手続きができ、混雑による待ち時間や交通コストを削減できる利点があります。
なお、申請時には登録免許税を現金、もしくは添付書類に収入印紙を貼る形で納付する必要があります。窓口で登記する場合、登記申請のタイミングによっては、法務局の混雑状況により審査までの時間が変動することもあるため、前もって確認しておくとスムーズです。
ステップ4書類審査を受ける
提出された申請書や添付書類は、法務局の登記官によって慎重に審査されます。内容に不備や記載漏れがある場合、補正や再提出を求められることがあるため、正確に書類を用意することが大切です。また、補正指示には期限が設けられており、超過すれば申請が却下されます。
司法書士に依頼している場合は、司法書士が窓口となって対応しますが、補正が必要な場合には依頼者の内容確認や書類への署名・押印が追加で必要になるケースもあります。適切かつ期限内に補正を済ませれば、申請は正式に受理され、所有権の移転が認められます。
ステップ5登記完了証を受け取る
審査が完了すると、法務局から「登記完了証」と「登記識別情報」が申請者に交付され、正式に新しい所有者として認められます。司法書士に依頼している場合は、書面またはデータ形式で司法書士から受け取ります。
登記識別情報は従来の登記済証に代わるものであり、自分が不動産の所有者であることを証明する大切な書類です。この書類が発行されて初めて、正式に不動産の新たな所有者として認められることになります。
所有権移転登記をする際の注意点2つ
所有権移転登記をする際は、以下の2点に注意する必要があります。トラブルを避けるためにも、十分留意して申請を進めましょう。
- 注意点1 申請は早めに行なう
- 注意点2 書類を紛失しないように注意する
ここでは、それぞれの注意点を解説します。
申請は早めに行なう
相続登記を除き、所有権移転登記を行なう法的な義務はありません。しかし、登記を行なわないと第三者に対して所有権を主張できないため、不動産を取得したときには速やかな申請が大切です。
また、2024年4月からは相続登記が義務化されており、未登記のままだと過料が科せられるようになりました。このような法的リスクを避けるうえでも、迅速かつ適切に手続きを進めましょう。
書類を紛失しないように注意する
登記手続きに必要な「登記識別情報」や「登記済証」は極めて重要な書類であり、紛失した場合の再発行はできません。
万が一紛失した場合でも、法務局側で登記名義人の本人確認を行なう「事前通知制度」や司法書士による本人確認情報の提供、公証人による認証などの方法を取ると登記手続きを進められます。しかし、いずれも手続きが複雑であり、方法によっては高額な費用が発生することがあります。
そのため、所有権移転登記完了後に受け取った登記識別情報は厳重に保管しておきましょう。
所有権移転登記の悩みは生和コーポレーションで解決
所有権移転登記の申請手続きは、専門的な知識が求められます。いざ申請が必要となったときに、相談先に悩む方も少なくありません。特に、登記手続きに加えて土地活用まで視野に入れている場合は、司法書士だけでは対応しきれないケースも考えられます。
申請に悩んだ際は、土地活用のプロである生和コーポレーションにご相談ください。土地活用や不動産管理、相続対策まで幅広く対応しており、不動産の専門家だからこその細かいサポートができるため、安心してお任せいただけます。
まとめ:所有権移転登記は正確かつ迅速に行おう
所有権移転登記は、不動産の購入や相続、贈与、財産分与の際に必要な手続きです。申請を怠ると、所有権を証明できず、トラブルに発展する可能性があります。
のちのトラブルを回避するためにも、不動産を取得したときには速やかに所有権移転登記を行なうことが大切です。
生和コーポレーションでは、登記申請はもちろん、土地活用に関するさまざまなサポートを行なっています。所有権移転登記をはじめ、不動産に関するお悩みを抱えている方は、お気軽にご相談ください。
関連記事:
土地・不動産売却の手続き・契約
他の「土地オーナー様のお悩み解決」の記事を見る
-
 将来を見据えて子や孫に財産を継承したいと考える一方で、贈与税や相続税の負担が気になる方も多いでしょう。 財産の継承方法には「生前贈与」と「相続」があり、特に生前贈与は、子や孫への投資、相続税対策、相続…
将来を見据えて子や孫に財産を継承したいと考える一方で、贈与税や相続税の負担が気になる方も多いでしょう。 財産の継承方法には「生前贈与」と「相続」があり、特に生前贈与は、子や孫への投資、相続税対策、相続… -
 不動産売却にあたって不動産会社と専任媒介契約の締結を検討しているものの、具体的な内容や手続きがわからずに不安を感じるオーナー様もいるのではないでしょうか。 専任媒介契約は、不動産の売却を不動産会社へ依…
不動産売却にあたって不動産会社と専任媒介契約の締結を検討しているものの、具体的な内容や手続きがわからずに不安を感じるオーナー様もいるのではないでしょうか。 専任媒介契約は、不動産の売却を不動産会社へ依… -
 土地活用において、神奈川県はとても魅力的な場所です。利用できる土地があれば、ぜひ有効に活用したいところです。それでは、どのような形で活用するのが最適なのでしょうか。 まず考えておきたいのは、神奈川県は…
土地活用において、神奈川県はとても魅力的な場所です。利用できる土地があれば、ぜひ有効に活用したいところです。それでは、どのような形で活用するのが最適なのでしょうか。 まず考えておきたいのは、神奈川県は… -
 土地所有者が自身の土地に建物を建設し、その建物を貸家として提供する場合の敷地を、貸家建付地と呼びます。貸家建付地には税額評価の際、自用地よりも評価額が低くなるという特徴があります。 本記事では、貸家建…
土地所有者が自身の土地に建物を建設し、その建物を貸家として提供する場合の敷地を、貸家建付地と呼びます。貸家建付地には税額評価の際、自用地よりも評価額が低くなるという特徴があります。 本記事では、貸家建… -
 土地活用の方法の1つに「事業用定期借地権」を利用した借地事業があります。これは一定期間、事業目的で土地を貸し借りする制度です。 本記事では、事業用定期借地権の概要や、活用に適した土地の特徴、土地に自ら…
土地活用の方法の1つに「事業用定期借地権」を利用した借地事業があります。これは一定期間、事業目的で土地を貸し借りする制度です。 本記事では、事業用定期借地権の概要や、活用に適した土地の特徴、土地に自ら…