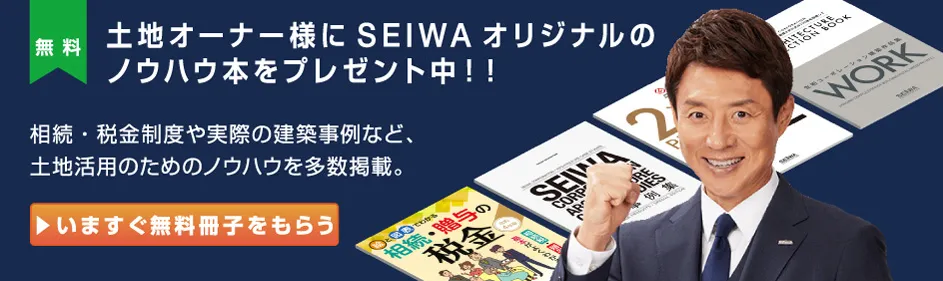「土地を借りて家を建てたい」、あるいは「土地を貸して収入を得たい」と考えているものの、「借地権の仕組みが複雑でよくわからない」「契約時に注意すべき点を知りたい」といった疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。
借地権は契約形態や適用される法律によって内容が異なり、理解が不十分なままではトラブルや将来の土地活用に影響が出る可能性があるため、注意が必要です。
この記事では、借地権の基本知識や種類、対抗要件、トラブルを防ぐために押さえておきたい契約時の注意点について解説します。
この記事の目次
借地権とは建物所有を目的とした土地の利用権
借地権とは、地主から借りた土地に建物を建てる権利です。借主(借地人)は地主に地代を支払う代わりに、一定期間その土地を使用できます。
一口に借地権といっても、「地上権」と「賃借権」の2種類に分けられます。地上権は、地主の承諾を得なくても土地上に建てられた家の売却、土地の転貸などが可能な権利です。一方、賃借権は土地上の家の建て替えや売却などを行なう際に地主の承諾が必要な権利を指します。地上権は地主にとって不利な側面があるため、借地契約では一般的に賃借権が用いられています。
借地権は借地借家法に基づく権利であり、地主から借りた土地に建物を建てることが前提となっています。そのため、駐車場や資材置き場など建物を建てない場合は、土地に借地権を設定できません。この場合は借地借家法ではなく民法が適用されます。
借地権付きの土地は、土地を所有しなくてもマイホームや事業用建物を建てられる手段として利用され、土地活用の一形態としても注目されています。
借地権の旧法と新法の違い
借地権は契約時期により以下の2種類に分かれます。
- 借地法(旧法):1992年7月31日以前の契約に適用
- 借地借家法(新法):1992年8月1日以降の契約に適用
借地権は、借地契約が結ばれた時期によって適用される法律が異なります。借地契約を交わした時期が1992年7月31日以前の場合は「借地法(旧法)」、同年8月1日以降の場合は「借地借家法(新法)」が適用されます。
適用される法律によって地主と借地人の権利関係が変わるため、現在の契約が旧法に基づくのか、新法に基づくのかを確認しておくことが重要です。
借地法(旧法)
「借地法(旧法)」は1992年7月31日以前に契約された借地に適用される法律です。特徴は借地人の権利が非常に強い点で、契約更新が原則として認められています。
また、建物の構造によって存続期間(契約期間)が次のように異なります。
- 木造などの非堅固建物:契約時20年(契約期間の定めがない場合は30年)、更新後20年
- 鉄筋コンクリート造などの堅固建物:契約時30年(契約期間の定めがない場合は60年)、更新後30年
旧法のもとでは、借地上に建物が建っていて地主側に正当な理由がない限り契約更新を拒否できません。そのため、借地人にとっては長期間にわたって安心して土地を使い続けられる一方で、地主にとっては土地の返還を求めるのが難しい側面があります。
借地借家法(新法)
1992年8月1日以降に契約された借地契約には、現行の「借地借家法(新法)」が適用されます。この法律は借地人保護の考え方を引き継ぎつつ、地主の資産活用や土地返還のしやすさにも配慮したバランスの取れた制度設計が特徴です。
借地借家法に基づく借地権は、「普通借地権」と「定期借地権」に大別されます。普通借地権は、原則として契約更新が認められる借地権です。それに対して定期借地権には契約更新がなく、契約期間の満了をもって契約が終了する点に違いがあります。
定期借地権はさらに契約目的に応じて「一般定期借地権」「事業用定期借地権」「建物譲渡特約付借地権」の3種類に分けられており、住宅用や事業用など用途に合わせた柔軟な活用が可能です。これにより地主は自らの土地活用方針に合わせて契約形態を選択でき、借地人にとっても利用目的に適した契約を結びやすくなっています。
普通借地権|契約更新が可能な借地契約
前章で触れたとおり、借地借家法に基づく借地権は「普通借地権」と「定期借地権」に分かれます。このうち普通借地権は、契約更新を前提とした借地契約であり、借地人の居住や利用を長期的に保障する仕組みです。
存続期間は建物の構造にかかわらず、次のように定められています。
- 契約時:30年以上
- 1回目の更新:20年以上
- 2回目以降の更新:10年以上
借地人が建物を使用し続けている限り原則として契約は更新されるため、実際には半永久的に土地を利用できるケースも少なくありません。地主の意向だけでは契約を終了できない点が特徴であり、借地人にとって安定性が高い契約形態といえます。
定期借地権の3種類|契約終了が明確な借地契約
借地借家法に基づく定期借地権には以下の3つがあります。
- 一般定期借地権
- 事業用定期借地権
- 建物譲渡特約付借地権
借地借家法に基づく借地権のうち、普通借地権は契約更新を前提としていますが、もう一方の定期借地権は契約期間終了とともに確実に土地が返還される仕組みです。
定期借地権はいずれも契約期間の満了をもって契約が終了するため、地主にとっては土地返還時期の見通しを立てやすく、資産活用の計画を描きやすいのが特徴です。一方で契約期間が明確である点は借地人にとってもメリットであり、長期利用や事業利用、短期利用など、目的に応じて柔軟に契約形態を選ぶことができます。
ここからは、一般定期借地権・事業用定期借地権・建物譲渡特約付借地権の3種類について、それぞれ詳しく見ていきましょう。
一般定期借地権
一般定期借地権は50年以上の契約期間を設定したときに適用される借地権で、建築する建物の用途に制限はありません。住居や介護施設など幅広い用途に利用されています。
契約の更新や地主への建物買取請求権の行使は認められておらず、契約終了後は原則借地人が建物を取り壊し、更地にして地主へ返還する必要があります。
ただし、借地人と地主の双方が合意すれば、契約満了後に新たな借地契約を締結でき、土地を引き続き利用することも可能です。
事業用定期借地権
事業用定期借地権は10年以上50年未満の期間で設定される借地権で、用途が店舗や事務所など事業用の建物に限定されている点に特徴を見いだせます。また、契約を締結する際は、公正証書によって行なわなければなりません。
契約期間が満了すると借地契約は終了し、借地人は建物を解体して土地を地主に返却する義務を負います。
事業用定期借地権の対象となるのは事業専用の建物に限られるため、賃貸マンションや住宅など居住を目的とした建物を建てるときには適用できません。一方で、ロードサイド店舗やコンビニエンスストアといった商業施設では、この仕組みを活用しているケースも多く見られます。
建物譲渡特約付借地権
建物譲渡特約付借地権は、契約終了後に地主が建物を相当価格で買い取ることをあらかじめ取り決めておく契約です。借地人は建物を取り壊すことなく土地を返還でき、地主は建物の所有権を取得できます。
建物譲渡特約付借地権は、建物が地主に譲渡された時点で消滅します。そのため、借地人が契約終了後もそのまま建物に住み続けたい、あるいは利用を継続したい場合には、建物の借家契約の締結が必要です。
土地活用のご相談、まずはお気軽に。相談から物件管理まで一貫したサポートを提供。
一時使用目的の借地権|一時的な事業目的で土地を借りるときの借地権
借地権には、普通借地権と定期借地権以外に「一時使用目的の借地権」と呼ばれるものも存在します。
一時使用目的の借地権は、イベント用の仮設建物や催事用仮設店舗、工事用の事務所・資材倉庫など土地の一時的な利用が明らかな場合に設定する権利です。借地借家法の適用対象外であるため、短期間の契約が可能で柔軟性が高い点が特徴です。
例えば、普通借地権では最低30年の契約期間が必要であるのに対し、一時使用目的の借地権では数年程度の契約でも認められます。
また、賃料が周辺相場より安い場合や、契約期間が数年と短いなどのケースでも、一時使用目的とみなされることがあります。
借地権は種類によって特徴が大きく異なるため、自分の目的に合ったものを選択することが大切です。
借地権の対抗要件とは?
借地権の対抗要件は、以下のいずれかを満たすことで備えられます。
- 借地権(地上権・賃借権)の登記
- 借地上の建物の登記
借地権の登記の有無を確認する際は、土地や建物の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して調べましょう。
借地権の対抗要件とは、借地権者(借地人)が第三者に対して自らの権利を主張するために必要な条件を指します。
地主と借地人の間で借地契約が成立していても、その効力は常に第三者におよぶわけではありません。
例えば、地主が土地を第三者に売却した場合、借地権者が対抗要件を備えていれば、所有者が変わっても土地を継続して使用する権利を主張できます。一方で、対抗要件を備えていなければ、当事者間で有効に成立した借地権であっても、第三者から土地の明渡しを求められた際に権利を主張できないおそれがあります。
対抗要件は、借地権者にとって借地を利用する権利を守るため欠かせないものです。また地主にとっても、借地権者が対抗要件を備えているかを把握しておくことは、将来的な土地の売却や相続をトラブルなく進めるうえで重要です。
借地権における対抗要件を備える方法
先述のとおり、借地権の対抗要件を備える方法には、借地権そのものを登記する方法と、借地上の建物を登記する方法があります。
ただし、実際には借地権の登記はまれで、後述の「建物の登記」による対抗要件取得が一般的となっています。
借地権(地上権・賃借権)の登記
借地権を第三者に主張する方法の一つが、土地の登記簿に借地権を記載することです。
前述のように借地権には「地上権」と「賃借権」があり、それぞれ登記の根拠や実務での取り扱いが異なります。
<地上権の場合>
地上権は物権であり、登記を行なえば第三者(新しい地主や抵当権者)に対抗できます。借地人には登記請求権が認められているため、地主の協力が得られなくても裁判を通じて登記を実現することが可能です。
ただし、地上権として借地契約が設定されるケースは少なく、実務では一般的ではありません。
<賃借権の場合>
賃借権は債権であり、原則として当事者間(地主と借地人)にしか効力を持ちません。しかし、土地の賃借権を登記すれば、第三者に対抗できます。
ただし、賃借権に登記請求権はないため、地主との合意が必要です。地主にとって賃借権登記は土地の処分に制限がかかるため、協力を得られにくく、実際に登記される例は限られています。
借地上の建物の登記
実務で広く利用されている対抗要件は、借地上に建てた借地人名義の建物を登記する方法です。
この場合、賃借権の登記がなくても、借地人は借地上の建物の登記を根拠に第三者に借地権を主張できます。地主が土地を売却しても、借地上の建物の登記によって借地人は新たな地主に対して借地権を主張でき、土地の使用を続けることが可能です。
一方で、建物が火災や地震などで失われた場合には、建物の登記に基づく対抗要件はなくなります。ただし、建物が失われてから2年以内であれば、借地上に「失われた建物を特定可能な事項」「失われた日」「再築予定の旨」を記載した看板などを設置すると、引き続き第三者に対抗できます。
借地権の登記の有無を確認する方法
借地権の登記があるかどうかは、土地の登記事項証明書(登記簿謄本)を調べればわかります。法務局またはオンラインで登記事項証明書を取得し、「権利部(乙区)」欄を確認しましょう。
乙区に「地上権設定」または「賃借権設定」との記載があれば、借地権が登記されていると判断できます。賃借権の場合は「原因」「目的」「賃料」「存続期間」「借地権者名」などの内容が記載されます。
借地権の登記が存在しない場合でも、建物の登記事項証明書を調べれば確認が可能です。建物の所有者として借地人の名前が記載されていれば、実質的に借地権が存在し、第三者に対抗できる状態にあるといえます。
借地権トラブルを防ぐ方法
借地権トラブルを防ぐには以下のポイントを押さえましょう。
- 契約書の内容を詳細かつ明確に作成・確認する
- 借地に精通した専門家に相談する
借地権は契約期間が長期におよぶうえ、地主・借地人双方の権利関係が複雑なため、思わぬトラブルに発展するおそれがあります。
ここでは、借地権をめぐるトラブルを未然に防ぐための方法を2つ紹介します。
契約書の内容を詳細かつ明確に作成・確認する
借地契約は契約年数が長いため、口約束や不十分な書面では将来的に認識の食い違いが生じやすくなります。そのため、契約は詳細を網羅した書面で交わすことが大切です。
地代の金額や増減の条件、建物の建て替え・譲渡・立ち退きの条件など、将来的に想定されるトラブルを見越して具体的に定めておきましょう。必要事項を漏れなく明記しておけば、借地人が亡くなって相続が発生した場合にも、その相続人との間で契約の一貫性を保てます。
契約書に不明点がある場合は自己判断せず、内容を正しく理解するためにも司法書士や弁護士などの専門家への相談を検討するとよいでしょう。
借地に精通した専門家に相談する
借地権は権利関係が複雑であるため、トラブルを未然に防ぐには借地に精通した実績豊富な専門家のサポートを受けることがポイントです。借地借家法や関連法規に詳しく、交渉力を備えた専門家を選べば、たとえトラブルが起きたとしても早期解決が期待できます。
例えば、借地分野に強い弁護士が所属している、あるいは弁護士事務所と提携している会社であれば、法的トラブルにもスムーズな対応が可能です。
売買や賃貸仲介に偏った会社では借地特有の問題に十分対応できない場合もあるため、借地契約に強い会社を選ぶことが契約全体の安心感につながるでしょう。
土地活用として借地契約をご検討の際は生和コーポレーションにご相談を
借地契約による土地活用をご検討の際は、生和コーポレーションにぜひご相談ください。当社では、借地契約による土地活用のご提案や関係者との交渉支援においても、数多くの実績を積み重ねてきました。
例えば、複数の法人や個人がかかわる土地に対し、借地契約を通じて賃貸物件を建設した事例があります。この案件では、複雑な権利関係の整理が必要でした。「土地をまとめて活用したい」というご要望に応えるため、粘り強い交渉と専門的なネットワークを活かし、複数の権利者との合意を形成して借地事業化を実現しました。
このように、生和コーポレーションは複雑な権利関係が絡む案件でもお客様のニーズに沿った借地契約の成立を支援し、土地の有効活用をサポートしています。借地権者からのご相談、底地権者からのご相談のいずれにも対応しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
まとめ:借地権の基本知識を理解して土地活用に役立てよう
借地権は、建物の所有を目的として土地を使用する権利であり、契約時期によって旧法(借地法)と新法(借地借家法)に分かれます。新法における借地権は契約更新が可能な「普通借地権」と、契約期間の満了により終了する「定期借地権」に大別され、それぞれ特徴が大きく異なるため、違いを理解することが大切です。
また、借地権に関するトラブルを未然に防ぐには、契約内容を明確にしておくことに加え、借地に精通した専門家のサポートを受けることが欠かせません。
生和コーポレーションは、50年以上の土地活用実績を活かし、借地契約を含む多様な活用プランを提案しています。借地権に関するお悩みを抱えている方は、ぜひお気軽にご相談ください。
関連リンク:
生和の土地活用の事例・実例はこちら
他の「土地活用方法・検討のポイント」の記事を見る
-
 RC造は、主要構造部や基礎が鉄筋とコンクリートで造られている構造です。耐火性や耐震性、耐久性などに優れていることから、低層~中高層の賃貸マンションやビル、戸建て住宅など多くの建造物に採用されています。…
RC造は、主要構造部や基礎が鉄筋とコンクリートで造られている構造です。耐火性や耐震性、耐久性などに優れていることから、低層~中高層の賃貸マンションやビル、戸建て住宅など多くの建造物に採用されています。… -
 不動産投資における「利回り」は物件の収益性 を示す指標であり、投資判断の基準として用いられます。これから不動産投資を始めるにあたり、利回りの高い物件を選びたいとお考えの方もいるのではないでしょうか。 …
不動産投資における「利回り」は物件の収益性 を示す指標であり、投資判断の基準として用いられます。これから不動産投資を始めるにあたり、利回りの高い物件を選びたいとお考えの方もいるのではないでしょうか。 … -
 不動産を取得すると、固定資産税や都市計画税、不動産取得税といった税金がかかります。特にマンションやアパート経営を始める際は、こうした税金を事業計画に組み込むことが欠かせません。 また、節税を目的に賃貸…
不動産を取得すると、固定資産税や都市計画税、不動産取得税といった税金がかかります。特にマンションやアパート経営を始める際は、こうした税金を事業計画に組み込むことが欠かせません。 また、節税を目的に賃貸… -
 マスターリースは「一括借上げ」とも呼ばれている賃貸物件の契約形態です。サブリース会社が物件のオーナー様から物件を一棟全体借り上げ、その物件を入居者に転貸することで賃料収入を得ます。 マスターリースには…
マスターリースは「一括借上げ」とも呼ばれている賃貸物件の契約形態です。サブリース会社が物件のオーナー様から物件を一棟全体借り上げ、その物件を入居者に転貸することで賃料収入を得ます。 マスターリースには… -
 土地のオーナー様のなかには、「店舗付き住宅」に興味がある方もいるのではないでしょうか。店舗付き住宅は、おもに1~2階にテナントが入った賃貸マンションを建てて経営する土地活用方法です。 この記事では、店…
土地のオーナー様のなかには、「店舗付き住宅」に興味がある方もいるのではないでしょうか。店舗付き住宅は、おもに1~2階にテナントが入った賃貸マンションを建てて経営する土地活用方法です。 この記事では、店…