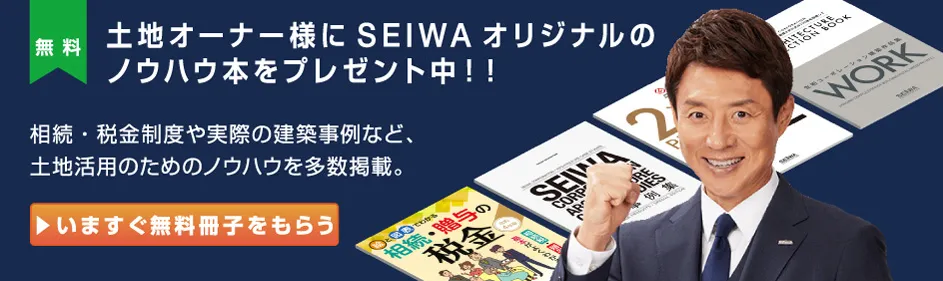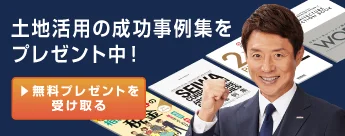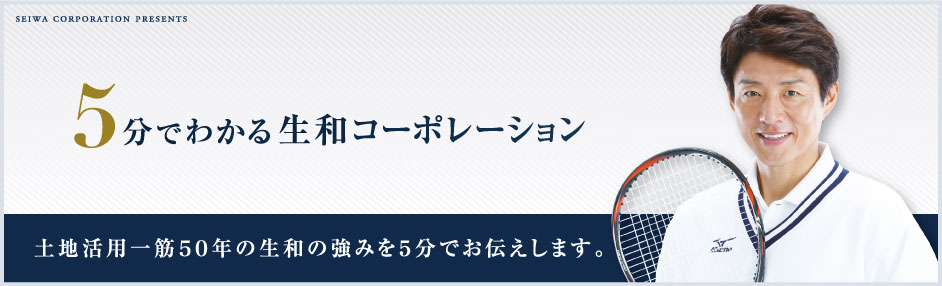アパート経営・マンション経営で不動産収入を得るには、いろいろな経費がかかります。
そのうち所得税法上、必要経費として認められた支出は控除の対象となります。
そこで今回は、アパート経営・マンション経営をしていく上で発生する必要経費について解説します。
本稿で言及している必要経費は、控除の対象として計上できる支出を指します。
この記事の目次
アパート経営・マンション経営をする上で認められている必要経費
アパート経営・マンション経営をする上で認められている必要経費は、家事上の経費と明確に区分できる必要があります。主なものとして上げられるのは、貸付資産に係る以下のような経費です。ただし、必要経費は確定申告や税務調査で厳しくチェックされるため、必要経費にできるかどうか判断に迷った場合は、必ず税理士など専門家に確認するようにしましょう。
・固定資産税
土地・建物を所有することにより発生する固定資産税。
・損害保険料
所有している賃貸住宅が加入している火災保険や地震保険などの損害保険料。
・減価償却費
建物、設備の経年による価値減少に相当する額を減価償却することができます。
不動産の場合、減価償却の対象となるのは建物部分の本体(躯体)と建物設備(電気設備・給排水設備など)の二つに大きく分かれます。建物部分だけで土地は対象ではありません。
本体の減価償却費は建物の耐用年数に応じて計上されます。そのため、建物の構造によって償却期間は異なり、法定耐用年数は鉄筋コンクリートが47年、重量鉄骨造が34年、木造が22年となっています。
建物設備の減価償却費は電気設備・給排水設備などに分けられますが、法定耐用年数はおおよそ15年となっています。
・修繕費/修繕積立金
アパート、マンションの維持管理費用(ペンキなどの塗り替え、畳、障子などの取り換え)、ドア、トイレ、台所、換気扇など設備の修理費用などは、修繕費として計上することができます。
なお増築を行った場合、増築部分は新たな資産となるため、かかった費用は修繕費ではなく減価償却の対象となります。
減価償却費と修繕費には区別の仕方があり、該当物件の使用可能期間が長くなったり、固定資産の価値を高めたりする場合の支出は資本的支出とみなされ減価償却費となります。
そして壁紙や床をキレイにするなど、原状回復とみなされるものは修繕費というように区別されています。
また修繕費の場合は減価償却とは違い、該当年に一括で経費として計上できるので、使い方によっては高い節税効果が得られます。
上記以外に必要経費として認められるものとしては、以下のような経費があります。家事上の経費と明確に区分することがむずかしく、混同しやすいものは、税理士など専門家と相談して適切に処理することが大切です。
・租税公課
アパートやマンションを購入したり、所有したりすることによって生じた税金。不動産取得税、事業税、印紙税などがあります。
・借入金利息
アパートやマンションなどを購入する際に借り入れした資金の利息は、経費として計上することができます。ただし、土地購入分の利息は経費計上できません。
・管理費
アパートやマンションの入居者様の募集、管理人や清掃業者など管理に伴う費用は必要経費として計上することができます。
・交通費
アパート経営・マンション経営に関わる交通費は経費として計上することができます。たとえば賃貸経営セミナーに参加するための交通費、物件を見に行くための交通費などです。また、車を利用している場合は、ガソリン代や駐車場代、高速料金、車検費用、自動車保険料、自動車税なども必要経費として計上できます。
・通信費
管理会社との電話通話料、物件検索をする際などのインターネット通信関連費用などは、通信費として計上することができます。
・新聞図書費
アパート経営・マンション経営に役立つ情報を収集するための新聞、書籍、雑誌等の購入費は、必要経費として計上することができます。
・接待交際費
管理会社や税理士など、アパート経営・マンション経営をする上で必要と認められる相手に対する接待交際費は、内容によっては必要経費として認められます。
・消耗品費
デジタルカメラ、パソコン、プリンターなどは、管理や業務上必要であれば、消耗品として経費計上することができます。
・その他
立ち退き料、弁護士報酬、税理士報酬なども、必要経費として計上することができます。
必要経費を計上する際の注意点
上記にあげた費用の中には、通信費などアパート経営・マンション経営に使用する部分とプライベートで使用する部分の線引きが難しいものがいくつかあります。それらを経費として計上する場合には、経費であることがわかるものを一緒に保管しておくなど、両者をきちんと分けておかないと、申告時に手間が増えるほか、経費計上を少なくせざるを得なくなってしまいますので注意が必要です。
個人事業主の必要経費の判断ポイントは、以下のようになります。
1.業務に直接関連するものである 。
該当経費がどの売上と対応するか明確であることが必要です。また、使用の目的も重要です。その経費が業務にどのように寄与したかも問われます。
2.業務遂行上、必要性がある。
3.業務用の金額を明確に区別できる。
個人事業主の必要経費として認められるのは以上の要件を満たすものです。そのため所得税・住民税は必要経費にはなりません。
また、不動産投資用にアパートなどの物件を新築した年は、減価償却費が最も大きくなり、不動産所得はほとんどの場合が赤字になりやすいです。物件を新築した年には、この点に注意し、その他の必要経費と合わせて節税効果をしっかり考慮した税務処理を行いましょう。
アパート経営・マンション経営で節税可能な税金とは
所得税
所得税は、必要経費が増加するほど節税することが可能になります。
というのも、以下のように算出する不動産所得の金額が、所得税の課税対象額になるからです。
総収入金額-必要経費=不動産所得の金額
したがって、必要経費が増加すればするほど、納めるべき所得税を軽減することが可能なのです。
また、小規模企業共済制度を利用することでも所得税の節税が可能です。
「小規模企業共済制度」とは個人事業主が積立金に応じた共済金を受領できる退職金制度で、この掛金の全額が所得控除の対象となります。
住民税
不動産投資における住民税の節税は「損益通算」によって可能となります。
損益通算とは、異なった費目の所得において、利益と損失を合計した結果に対して課税が行われることです。
給与所得と不動産所得を損益通算することができるため、不動産所得が赤字の場合、給与所得から不動産所得のマイナス分を差し引き、住民税の課税対象所得を減らすことができるという流れです。
相続税
相続税は土地の評価額によって変わってきます。
たとえば、もし何もない土地を相続した場合は、マンションなどの賃貸物件を建設すると、更地の場合やマイホーム建設の場合より評価が低くなります。その結果、相続税が下がります。
固定資産税
先述のように、マンションなどを建てた土地は更地より評価額が下がります。およそ2割下がったというデータもあります。これは土地の評価だけではなく、建物自体の評価も影響を受けます。
賃貸物件の場合、自己の持ち家と比較すると評価はおよそ7割に下がります。
このように賃貸物件を立てると、固定資産としての評価が大きく下がるので、当然の結果として固定資産税が軽減されます。
関連リンク:アパート・マンション・賃貸経営の税金対策・節税の方法損益通算を利用しよう
所得税・住民税・相続税の節税対策として不動産投資は確実に効果を得られますが、ここで上記の住民税の項に出てきた「損益通算」に関して説明します。
アパート経営・マンション経営による不動産投資の所得が赤字となった場合、本業で給与所得がある方は、給与所得から源泉徴収されている所得税の還付が受けられるという大きなメリットが生まれます。
不動産所得では、損失をその他の黒字となっている所得と通算して課税所得を計算する事が認められているからです。それが損益通算です。
なお、損益通算が可能な所得は限られており、不動産所得はその一つです。ただし、不動産所得の中でも土地などの取得に係る借入金利子部分や、分離課税の対象となる譲渡所得(土地建物など)の計算上生じた損失は、対象にはならないので注意が必要です。
また、所得税が軽減されるので、軽減された所得税をベースに計算される翌年の住民税も当然軽減されます。
このような損益通算による節税効果は確定申告によって得られます。そのため、個人事業主にとって確定申告は収支の鍵を握る大切なポイントです。
土地活用のご相談、まずはお気軽に。相談から物件管理まで一貫したサポートを提供。
これは経費?経費にまつわる疑問を解決
経営には様々な出費があり、中には経費とできるのか判断しづらいものもあります。ここでは、どこまでが必要経費となるか判断しづらいパソコンと車にまつわる費用について取り上げて確認していきましょう。
1)パソコンを買った場合、経費にできるのか
購入物件に関する情報収集や確定申告書類の作成などで活躍するパソコンも、経費となる場合とそうでない場合があり、いくつかのボーダーラインがあります。
≪購入価格が10万円未満の場合≫
10万円未満のパソコンについては、消耗品費として経費にできます。ただし、マウスやモニター等もセットで考える必要があるため、合計金額に注意が必要です。
≪購入価格が10万円以上30万円未満の場合≫
10万円以上のパソコンは固定資産扱いのため減価償却が必要です。パソコンの法定耐用年数は4年ですから、通常は4年かけて償却します。ただし、この価格帯には以下2つの特例があります。
| 一括償却資産 | 10~20万円未満であれば、一括償却資産として3年で償却できる |
|---|---|
| 少額減価償却資産 (青色申告者のみ) |
青色申告者は10~30万円未満であれば一括で経費とすることが可能。 ただし、300万円の年間限度額、『少額減価償却資産の取得価格に関する明細書』の提出、平成30年3月31日までに購入したものという条件付き。 |
≪購入価格が30万円以上の場合≫
固定資産ですので、法定耐用年数による減価償却が必要です。
ちなみに、パソコンが家庭用と兼用の場合であっても、上記のボーダーラインは変わりません。購入総額から減価償却費を算出し、その後に按分した事業用割合を申告します。(確定申告書類もその流れで記載できるよう作られています。)なお、パソコン同様、インターネット接続料金についても家庭用と按分しますが、事業按分は3~4割とされることが多いようです。
2)車にまつわる費用は経費にできるのか
例えば、自宅から離れた場所にある所有物件の管理に、私用でも使う自動車で向かう場合、自動車ローンやガソリン代、駐車場料金、車検費用、修理費用などは、経費になるのでしょうか。
まず、ローンの元本については、勘定科目でいう車両運搬具であり固定資産となるため、減価償却をすることになりますが、ローンの金利については経費とすることができます。車検や修理費用、駐車場代、保険料等も経費にできます。
ただし、自動車自体に私用の用途がありますから、家事用と事業用で按分します。判断基準は走行距離とされることが多いようです。家事用と按分する場合、税務署を納得させられる合理的な基準や根拠が必要となりますから、按分が必要となる経費については、記録をとる、証明できる書類等は確実に保管するなどの対策をとると安心でしょう。
経費を正しく計上して節税につなげよう
1)不動産所得がある場合の税金の計算方法と節税の仕組み
アパート経営・マンション経営を始め、順調に家賃等の収入が入っている状態だとしても、年間の収支は確定申告が完了するまで明確にはなりません。ここで、1-1でも触れた、所得税の計算方法について少し説明しましょう。
収入にも経費にも、算出するために様々な手順はありますが、基本的に、下記が所得の計算方法です。
【 所得=収入-経費 】
次に所得控除を行い、課税所得を算出。
課税所得に税率を掛け、必要に応じて税額控除をすると、納税額が現れます。
【 課税所得=所得-所得控除 】
【 納税額=課税所得×税率-税額控除 】
所得税の税率は累進課税のため、所得額に応じて税率も上がります。そのため、所得をいかに抑えるかが節税には重要であり、基本と言える式【 所得=収入‐経費 】にある経費は、重要な存在なのです。また、住民税や国民健康保険、事業税なども所得を根拠に計算されますから、生活における最終的な収支を考えると、経費の重要性はさらに高まります。
ちなみに、「所得が20万円を超えると確定申告をしなければならない。」という義務のイメージが強いですが、確定申告は税金を納めるためだけのものではありません。不動産所得以外の給与所得等があり、不動産所得がマイナスの場合は、源泉徴収で既に支払っている税金を返金してもらうことができます。これを損益通算と言いますが、経費がかさみ所得がマイナスになりやすい初年度には、特に見逃せないシステムです。これも節税のひとつですね。
2)アパート経営・マンション経営における確定申告の方法と流れ
では、確定申告には、どのような準備や手順が必要なのでしょう。確定申告の時期や準備すべきものを認識すれば、アパート経営・マンション経営初年度から、経費も意識しやすくなります。
≪確定申告の時期≫
確定申告は、毎年2月16日から3月15日に税務署で行います。税務署に必要書類を直接提出するか、郵送(信書扱い)、電子公告(e-Tax)の方法があり、自分に合った方法を選びます。確定申告期間を過ぎると、無申告加算税等の追徴課税が発生しますから、必ず期限内に申告できるよう事前準備が必要です。
≪確定申告に必要な書類≫
確定申告には、青色申告と白色申告の方法があります。どちらの方法も書類の種類は多くありませんが、青色申告は特別控除や損失繰り越しのメリットが大きい分、所得税青色申告決算書の内容自体が濃く、申告書類を作成するために必要な経理上の記録(控除関係書類等)も多くなります。また、青色申告のメリットを享受するためには、事前に『所得税の青色申告承認申請書』や『青色事業専従者給与に関する届出書』なども必要です。一方、白色申告は収支内訳書がシンプルで全体的な手間が少なくなりますが、青色申告のようなメリットはありません。
確定申告には、以下のような書類が必要です。
| 申告種類 | 必要書類 | 注意事項 |
|---|---|---|
| 青色申告 | 確定申告書B 確定申告書に添付する控除関係書類 所得税青色申告決算書(不動産所得用) |
事前に『所得税の青色申告承認申請書』『青色事業専従者給与に関する届出書』等手続きが必要。 |
| 白色申告 | 確定申告書B 確定申告書に添付する控除関係書類 収支内訳書(不動産所得用) |
白色であっても、平成26年から帳簿記帳とその保管が義務化されたため、保存期間の変更に注意が必要。 |
※国税庁ホームページにて書類の詳細が確認できます。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/02.htm
両者に共通して重要なのは、確定申告書類の根拠となる数字(資料)の管理です。源泉徴収票や保険証券、控除関係書類、固定資産税通知書、物件価格が明記される売買契約書や賃貸借契約書など、アパート経営・マンション経営に関わるものは、種類別や時系列で管理することが正しい帳簿の作成に繋がります。特に経費は細かいものや按分等がありますから、領収書に用途を記載する、按分のために自動車の走行記録をつけるなどの工夫が、後々の確定申告に役立つでしょう。
≪確定申告の主な流れ≫
確定申告の時期と必要書類がイメージできると、確定申告までの流れもイメージしやすくなります。白色はシンプルなためここでの説明は省略しますが、、青色申告で流れを追うと、以下のようになります。
1.確定申告書類と、前述した確定申告に必要な資料を用意
確定申告書類は、アパート経営・マンション経営開始時に『事業の開業・廃業等届出書』を提出していれば手元に届きますが、国税庁HPよりダウンロードもできます。
2.準備した資料に基づき、所得税青色申告決算書(不動産所得用)に記入
この決算書の記入で、不動産所得がわかります。
3.確定申告書Bの記入
所得税青色申告決算書が完成すると、確定申告書Bへの記入ができ、課税所得額と所得税の納税額が明らかになります。
4.税務署へ確定申告書類を提出
確定申告書が完成したら、税務署に提出します。
5.税金を納付する
確定申告で納税額が決定し、期間内に金融機関で納付します。納付書(所得税徴収高計算書)は税務署か、確定申告期間内であれば金融機関でも手に入ります。また、還付がある場合は、指定口座に振り込まれます。
経理等の経験者でないと、未知の用語が多く難しく感じる確定申告ですが、手順を踏めば恐れることはありません。会計ソフトの作りも親切ですし、税務署(確定申告会場)でも、不明点は親切に教えてくれます。確定申告で所得税が決定するということは、アパート経営・マンション経営の一年間の収支が決定するということですから、臆することなくぜひ取り組んでください。
アパート経営・マンション経営の最適な経費率
アパート経営・マンション経営の経費率を15%や20%として、各物件情報に当てはめて検討することがあるようですが、この考え方はどの物件にも通用すると一概には言えません。なぜなら、一覧表示される物件情報は、比較検討しやすくするために、全物件に共通するシンプルな情報のみで構成されることが多いためです。物件は、大きく分けただけでも、規模、築年数、建築方法、立地などの特徴があります。掘り下げれば限りはないでしょう。
この特徴に対し、経費率を一律で考えていくことには無理があります。例えば、似通った物件であっても、エレベーターの有無で発生する費用は大きく変わります。和の趣を持つ物件と、人気のカフェをイメージした物件で、同じ修繕費になるとも考えづらいところです。
経費率はあくまでも目安です。現実に近い経費を予測するためには、物件ごとの特徴をよく知り、発生する費用を時系列に想定するなどの作業が必要となってくるでしょう。そのため、一般的と言われる15~20%の経費率を使用するのは、物件一覧を見比べる最初のみとして、これぞと思う物件を見つけたら、詳しく調べることをおすすめします。
適切な経費計上で上手に節税を
アパート経営・マンション経営には固定資産税・損害保険料・減価償却費・修繕費・租税公課・借入金利息・管理費・交通費・通信費・接待交際費・新聞図書費・消耗品費が必要経費として認められます。これらを適切に計上することだけでも、ある程度の節税効果は得られるでしょう。
ですが、不動産投資は税金対策の占める割合が高い投資です。専門家のアドバイスを受けて税金対策も含めた収支計画を実行しましょう。
※写真はイメージです
※本記事は、2018年9月以前時点の情報をもとに執筆しています。 マーケットの変化や、法律・制度の変更により状況が異なる場合があります
※記事中では一般的な事例や試算を取り上げています。個別の案件については、お気軽にお問い合わせください。
- 関連するタグはこちら
他の「失敗しないアパート経営」の記事を見る
-
 サラリーマンなど給与所得を受けている人は、勤めている会社が税務処理を行ってくれるため、自分では何もする必要がありません。しかし、アパート経営・マンション経営をはじめて、給与所得とは別に年間20万円以上…
サラリーマンなど給与所得を受けている人は、勤めている会社が税務処理を行ってくれるため、自分では何もする必要がありません。しかし、アパート経営・マンション経営をはじめて、給与所得とは別に年間20万円以上… -
 アパート経営・マンション経営はしっかり対策を講じることで高い相続税対策の効果が得られます。近い将来に土地の相続を予定している人にとっては、アパート経営・マンション経営を行うことで相続税対策になることは…
アパート経営・マンション経営はしっかり対策を講じることで高い相続税対策の効果が得られます。近い将来に土地の相続を予定している人にとっては、アパート経営・マンション経営を行うことで相続税対策になることは… -
 アパート経営・マンション経営を始めると、たとえ小規模でも確定申告をして納税する義務が生じます(給与所得者で不動産所得が年間20万円以下の場合など、条件によっては免除されることもあります)。 確定申告は…
アパート経営・マンション経営を始めると、たとえ小規模でも確定申告をして納税する義務が生じます(給与所得者で不動産所得が年間20万円以下の場合など、条件によっては免除されることもあります)。 確定申告は… -
 アパート経営・マンション経営を開始して所得が発生すると、確定申告を行って納税する必要が出てきます。もともと自営業などを営んでいて、毎年確定申告を行っていた人なら問題ありませんが、会社員の方など確定申告…
アパート経営・マンション経営を開始して所得が発生すると、確定申告を行って納税する必要が出てきます。もともと自営業などを営んでいて、毎年確定申告を行っていた人なら問題ありませんが、会社員の方など確定申告… -
 サラリーマンの副業としてアパートマンション経営を行っている方もいらっしゃいますが、気になるのは税金に関することではないでしょうか。 給与所得以外にも不動産収入が得られることで、支払う税金の額が多くなっ…
サラリーマンの副業としてアパートマンション経営を行っている方もいらっしゃいますが、気になるのは税金に関することではないでしょうか。 給与所得以外にも不動産収入が得られることで、支払う税金の額が多くなっ…
他の「失敗しないマンション経営」の記事を見る
-
 マンション経営を続けていくうえで「法人化すべきかどうか」は、多くのオーナー様が判断に悩まれるのではないでしょうか。 法人化は税金面でのメリットが期待できる一方、設立時のコストや煩雑な会計処理といった負…
マンション経営を続けていくうえで「法人化すべきかどうか」は、多くのオーナー様が判断に悩まれるのではないでしょうか。 法人化は税金面でのメリットが期待できる一方、設立時のコストや煩雑な会計処理といった負… -
 マンション経営においては、誰もが「経営に失敗したくない」「赤字になりたくない」と考えるでしょう。 マンション経営の赤字は、「問題ない赤字」と「対処が必要な赤字」に分けられます。後者の状態になってしまっ…
マンション経営においては、誰もが「経営に失敗したくない」「赤字になりたくない」と考えるでしょう。 マンション経営の赤字は、「問題ない赤字」と「対処が必要な赤字」に分けられます。後者の状態になってしまっ… -
 サラリーマンなど給与所得を受けている人は、勤めている会社が税務処理を行ってくれるため、自分では何もする必要がありません。しかし、アパート経営・マンション経営をはじめて、給与所得とは別に年間20万円以上…
サラリーマンなど給与所得を受けている人は、勤めている会社が税務処理を行ってくれるため、自分では何もする必要がありません。しかし、アパート経営・マンション経営をはじめて、給与所得とは別に年間20万円以上… -
 アパート経営・マンション経営はしっかり対策を講じることで高い相続税対策の効果が得られます。近い将来に土地の相続を予定している人にとっては、アパート経営・マンション経営を行うことで相続税対策になることは…
アパート経営・マンション経営はしっかり対策を講じることで高い相続税対策の効果が得られます。近い将来に土地の相続を予定している人にとっては、アパート経営・マンション経営を行うことで相続税対策になることは… -
 アパート経営・マンション経営を始めると、たとえ小規模でも確定申告をして納税する義務が生じます(給与所得者で不動産所得が年間20万円以下の場合など、条件によっては免除されることもあります)。 確定申告は…
アパート経営・マンション経営を始めると、たとえ小規模でも確定申告をして納税する義務が生じます(給与所得者で不動産所得が年間20万円以下の場合など、条件によっては免除されることもあります)。 確定申告は…