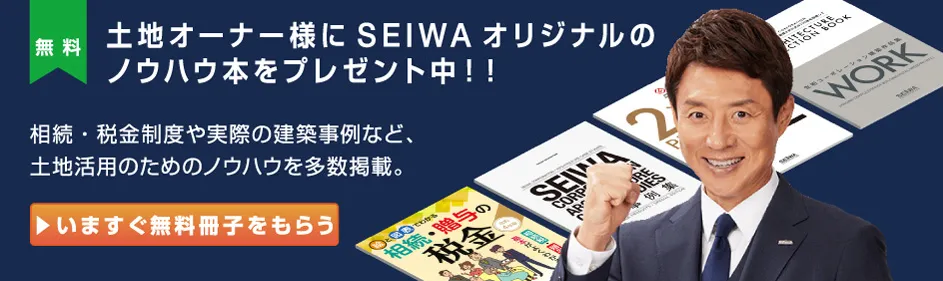相続によって不動産を取得すると相続税がかかります。また、不動産を所有しているだけでも毎年固定資産税がかかります。賃貸併用住宅は、相続税や固定資産税の節税対策になると言われていますが、ここでは節税の仕組みや、どの程度の節税効果を期待できるのかについて解説します。
賃貸併用住宅の相続税評価額はどのように計算する?
相続税を計算するときに土地や建物を評価する必要があります。建物は、原則として固定資産税評価額が相続税評価額となります。これは新築の場合、概ね建物の建築費の約40~50%が目安とされています。
宅地の評価方法には2種類ありますが、市街地にある場合は、道路に面する1平方メートルあたりの価額に、宅地の形状に合わせて補正して計算する「路線価方式」で評価します。また、路線価が定められていない地域の土地では固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて計算する「倍率方式」で評価します。さらに、土地には自分のために使用している「自用地」や、自分の土地に賃貸物件を建てて他人に貸している「貸家建付地」などがあり、評価の方法に違いがあります。それぞれの評価額の計算法は以下の通りです。
・自用地の評価額の計算方法
【路線価×奥行価格補正率×地積】
・貸家建付地の評価額の計算方法
【自用地評価額-自用地の評価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合】
ただし、借地権割合と借家権割合は地域によって異なるので、路線価図などで確認することが必要です。
上記の計算方法を見てわかる通り、賃貸併用住宅や貸店舗などは貸家建付地評価額と見なされ、自用地の評価額から一定の割合を減額(概ね79%に減額)できるため、自宅のみの場合より評価額を低くすることができ節税に効果があると言えるわけです。
土地活用のご相談、まずはお気軽に。相談から物件管理まで一貫したサポートを提供。
小規模宅地等の評価額の特例とは?
小規模宅地等の評価額の特例とは、高額な相続税が課された場合、相続人が居住したり事業を引き継いだりすることができなくなってしまうのを防ぐ制度です。一定の要件を満たした宅地では、通常の評価額から一定の割合で減額することができます。
例えば、被相続人の配偶者や同居の子どもが自宅を相続する場合は、特定居住用宅地と区分され、最大330平方メートルまで80%評価減の特例対象となります。しかし、被相続人である親と同居しない子どもが相続すると特例を受けられなくなるケースがあります。一方、賃貸併用住宅では、賃貸部分については貸付事業用宅地等として区分され、最大200平方メートルまで50%評価減の対象になります。これは、被相続人である親と同居していなくても対象になります。この特例が適用されれば相続税の評価額を大きく減額することができるため、自宅のみの住宅を相続する場合と比べ、賃貸併用住宅を相続することは、相続税の節税対策として大きなメリットとなるでしょう。
関連記事はこちら:「賃貸併用住宅の上手な節税・減税対策とは」
賃貸併用住宅はどうして固定資産税対策になる?
固定資産税は、建物や土地を所有しているだけで毎年課税されるものです。自宅や賃貸住宅は、住宅用地になるので固定資産税の課税標準を減額する特例もあります。その特例では、敷地面積が200平方メートル以下の部分は固定資産税評価額が6分の1に、200平方メートルを超える部分は3分の1として算定します。これは、一戸あたりで判断されるので、自宅のみの場合は一戸分だけですが、賃貸併用住宅では自宅を含めた戸数分が特例の対象になります。つまり自宅と賃貸戸数の合計が5つになれば、200平方メートル×5=1000平方メートルまでが6分の1の減額特例の対象になります。そのため、200平方メートルを大きく超える広い土地に建てる場合ほど、賃貸併用住宅の方が自宅のみの戸建て自宅を建てるよりも固定資産税の節税効果が大きくなると言えます。
相続税や固定資産税の特例が適用されるかどうかの判断はなかなか難しいかもしれません。節税効果を期待して賃貸併用住宅を建てたのに、特例を受けることができないとローン返済等の資金繰りに大きな負担になってしまいます。賃貸併用住宅の節税効果については自分で判断するのではなく、税理士など専門家に相談するようにしましょう。
- 関連するタグはこちら
他の「土地オーナー様のお悩み解決」の記事を見る
-
 将来を見据えて子や孫に財産を継承したいと考える一方で、贈与税や相続税の負担が気になる方も多いでしょう。 財産の継承方法には「生前贈与」と「相続」があり、特に生前贈与は、子や孫への投資、相続税対策、相続…
将来を見据えて子や孫に財産を継承したいと考える一方で、贈与税や相続税の負担が気になる方も多いでしょう。 財産の継承方法には「生前贈与」と「相続」があり、特に生前贈与は、子や孫への投資、相続税対策、相続… -
 不動産売却にあたって不動産会社と専任媒介契約の締結を検討しているものの、具体的な内容や手続きがわからずに不安を感じるオーナー様もいるのではないでしょうか。 専任媒介契約は、不動産の売却を不動産会社へ依…
不動産売却にあたって不動産会社と専任媒介契約の締結を検討しているものの、具体的な内容や手続きがわからずに不安を感じるオーナー様もいるのではないでしょうか。 専任媒介契約は、不動産の売却を不動産会社へ依… -
 不動産の売買や相続、贈与などで所有権の名義が変わる場面では「所有権移転登記」が必要です。しかし、何から始めればよいかわからず、手続きを後回しにする方は少なくありません。 また、税負担や債権者からの差押…
不動産の売買や相続、贈与などで所有権の名義が変わる場面では「所有権移転登記」が必要です。しかし、何から始めればよいかわからず、手続きを後回しにする方は少なくありません。 また、税負担や債権者からの差押… -
 土地活用において、神奈川県はとても魅力的な場所です。利用できる土地があれば、ぜひ有効に活用したいところです。それでは、どのような形で活用するのが最適なのでしょうか。 まず考えておきたいのは、神奈川県は…
土地活用において、神奈川県はとても魅力的な場所です。利用できる土地があれば、ぜひ有効に活用したいところです。それでは、どのような形で活用するのが最適なのでしょうか。 まず考えておきたいのは、神奈川県は… -
 土地所有者が自身の土地に建物を建設し、その建物を貸家として提供する場合の敷地を、貸家建付地と呼びます。貸家建付地には税額評価の際、自用地よりも評価額が低くなるという特徴があります。 本記事では、貸家建…
土地所有者が自身の土地に建物を建設し、その建物を貸家として提供する場合の敷地を、貸家建付地と呼びます。貸家建付地には税額評価の際、自用地よりも評価額が低くなるという特徴があります。 本記事では、貸家建…